精神疾患の原因とは?診断基準・受診の目安・相談先まで徹底解説
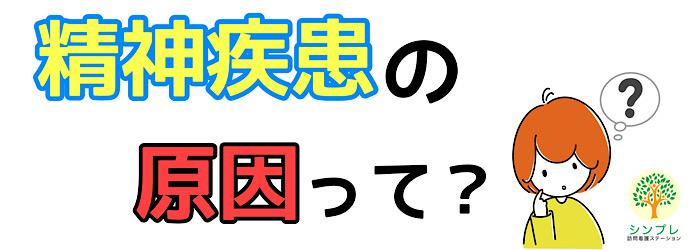

精神疾患の原因は一つではなく、遺伝や脳の働き、性格やトラウマ、社会環境などが複雑に関わり合って発症すると考えられています。
現在も研究が進められていますが、まだ解明されていない部分も多くあります。
そのため、「なぜ自分が精神疾患を発症したのか」と不安に思う方も少なくありません。
この記事では、精神疾患の原因をわかりやすく整理し、診断基準や受診の目安、相談先について解説していきます。
ご自身やご家族が心の不調に悩んでいる場合の参考にしてください。
精神疾患の原因とは?

精神疾患の原因は一つに限定されるものではなく、複数の要因が重なり合うことで発症すると考えられています。
大きく分けると、遺伝による影響、脳や体の働きによる生物学的要因、性格やトラウマなどの心理的要因、人間関係や職場環境といった社会的要因があります。
どの要因が強く作用するかは人によって異なり、またそれぞれが相互に関係し合うことで症状が表れるケースも多いのです。
遺伝による影響
精神疾患の発症には遺伝が関係していると考えられています。
家族の中で特定の精神疾患が繰り返し見られる場合や、遺伝子の変化が神経伝達物質の働きに影響を及ぼすことがあると指摘されています。
ただし、遺伝はあくまで「発症しやすさ」を高める要因のひとつであり、必ずしも遺伝だけで精神疾患が起こるわけではありません。
脳や体の働きによる生物学的な要因
脳の構造や働きの異常は、精神疾患の原因と深く関わっています。
例えば、前頭前野や扁桃体の働きの乱れは不安障害や強迫性障害と関連があるとされます。
また、甲状腺機能異常(亢進症・低下症)や脳血管障害などの身体疾患が精神症状を引き起こすこともあります。
統合失調症や双極性障害では脳の神経伝達に異常が見られることがあり、医学的な研究が続けられています。
性格やトラウマなど心理的な要因
- 不安やトラウマ
- 人間関係の問題
- 仕事や学校のストレス
- 経済的な問題
過度のストレスや心理的なトラウマは、うつ病やPTSDのリスクを高める可能性があります。
特に、几帳面で完璧主義な性格の方はストレスを抱え込みやすく、発症リスクが高まることがあります。
また、人間関係の葛藤や過去の体験が心に影響を残し、精神疾患につながるケースも少なくありません。
人間関係や職場環境など社会的な要因
家庭環境や職場の人間関係、いじめやハラスメントなどの社会的要因も大きな影響を与えます。
虐待やいじめを受けた経験がある人は、うつ病や不安障害を発症するリスクが高いといわれています。
社会的孤立や経済的な困難も心の健康を損なう要因になり得ます。
精神疾患は誰にでも起こりうるものであり、不調を感じたら一人で抱え込まずに早めに相談することが大切です。
精神疾患の診断基準をわかりやすく解説
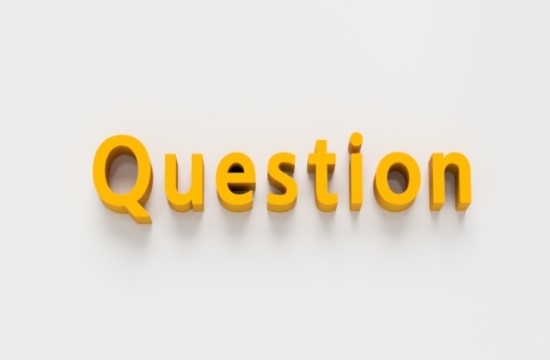
精神疾患の診断は医師の経験や問診だけでなく、国際的に定められた診断基準を用いて行われます。
なぜなら、精神疾患の原因や症状は多様で、患者さんごとに大きな差があるからです。
そのため、客観的な基準をもとに診断することで、治療方針を立てやすくし、誤診を防ぐ役割を果たしています。
ここでは世界保健機関(WHO)が定める『ICD』と、アメリカ精神医学会がまとめた『DSM』という二つの代表的な診断基準をご紹介します。
世界保健機関(WHO)の『ICD-10』と最新の『ICD-11』
WHO(世界保健機関)が策定した『ICD-10』(国際疾病分類第10版)は、精神疾患だけでなく、身体疾患も含めた幅広い診断基準が掲載されている国際的なルールブックです。
ICD-10は医療機関での診断や行政上の統計に利用され、世界中で共通の診断基準として活用されています。
精神疾患の診断においては、うつ病や統合失調症、不安障害などが細かく分類されており、症状や発症経過を整理する際の重要な指標となります。
また近年は約30年ぶりに改訂された『ICD-11』が登場し、ゲーム障害や性別不合といった新しい疾患分類も導入されました。
ICD-11は最新の研究成果を反映したものであり、精神疾患の原因や背景をより的確にとらえるための診断体系として世界的に普及が進められています。
アメリカ精神医学会の『DSM-5』とは
アメリカ精神医学会が発行している『DSM-5』(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)は、精神科医が臨床の現場で用いる標準的なガイドラインです。
DSM-5では、精神疾患が22のカテゴリーに分けられ、それぞれのカテゴリーはさらに細かく分類されています。
これにより、症状の特徴や持続期間、生活への影響などを基準にして、より正確な診断が行えるようになっています。
ICDが国際的な行政や統計に多く用いられるのに対し、DSMは臨床現場での「共通言語」として活躍しています。
例えば、うつ病と適応障害は症状が似ている部分もありますが、DSM-5の基準に基づくことで、原因の整理や治療法の選択がより適切に行えるのです。
診断基準を正しく用いることは、患者さん一人ひとりの背景にある精神疾患の原因を理解し、効果的な治療へとつなげる大切なステップになります。
精神疾患の診断方法
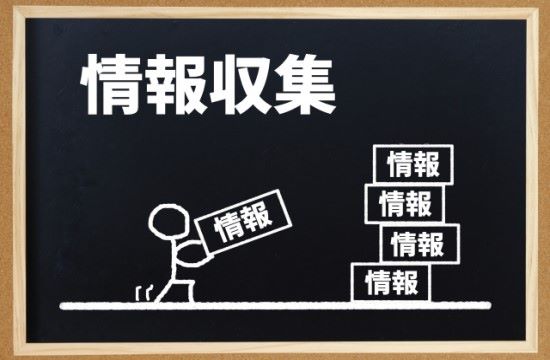
精神疾患の診断は、問診や検査を通じて慎重に行われます。
なぜなら、精神疾患は原因や症状が多岐にわたり、似たような症状でも別の疾患であることが多いからです。
そのため、精神科医は患者さんの症状だけでなく、生活背景や既往歴、家族歴までを含めて総合的に判断していきます。
ここでは、実際に医療現場で行われる診断の流れについて解説します。
問診を中心とした診断の流れ
精神科や心療内科を受診すると、まずは問診が行われます。
問診では、症状がいつから始まったのか、どのような経過をたどっているのか(現病歴)、過去の病歴やケガ(既往歴)、家族に精神疾患があるかどうか(家族歴)などを丁寧に確認します。
さらに、生活習慣や人間関係、仕事や学校での状況など、社会的な背景についても聞き取りが行われます。
このように多角的に情報を集めることで、精神疾患の原因に関連する要素を把握し、適切な診断へとつなげることができます。
例えば「気分が落ち込む」という症状一つをとっても、うつ病だけでなく適応障害や双極性障害など複数の可能性があるため、詳細な問診が欠かせません。
頭部CT・MRI・血液検査などを行う場合もある
精神疾患の診断では基本的に問診が中心ですが、必要に応じて検査を行うこともあります。
脳腫瘍や脳血管障害などの器質的疾患の除外には、頭部MRIによる画像検査が重要です。認知症の診断は問診・認知機能検査が中心となり、画像検査は鑑別診断や器質的疾患の除外目的で必要時に実施されます。
また、甲状腺機能の低下や膠原病など身体的な病気が精神症状の原因になっている場合もあるため、血液検査を実施することもあります。
これらの検査は、精神疾患そのものを直接「見つける」ためというより、他の身体疾患による影響を除外する目的で行われます。
正確な診断を下すためには、精神症状だけでなく身体面からの確認も欠かせません。
十分な問診と検査の結果を合わせることで、精神科医は最終的に診断を行い、その後の治療方針を決定していきます。
診断はゴールではなく、治療やサポートの第一歩です。
精神疾患の原因は複雑で一人ひとり異なりますが、正確な診断を受けることで、その方に合った治療法や生活支援を見つけることができます。
不安を感じたら早めに医療機関へ相談することが大切です。
精神疾患で医療機関を受診する目安

精神疾患は誰にでも起こりうるものであり、原因も症状も人によって異なります。
そのため、「これは精神疾患なのでは?」と判断するのは簡単ではありません。
しかし、体や心に一定期間続く変化が現れたときは、受診を検討するサインといえます。
ここでは、体に現れる変化と心に現れる変化に分けて、医療機関を受診する目安を解説します。
体に現れる変化
睡眠障害がある
寝付きが悪い、夜中に何度も目が覚める、早朝に目が覚めて眠れないといった症状が続く場合は注意が必要です。
うつ病では9割以上に睡眠障害が見られるといわれており、強いストレスや精神疾患の原因が背景にあることもあります。
単なる「一時的な不眠」と軽視せず、2週間以上続く場合は医療機関に相談しましょう。
食欲不振・頭痛などが2週間以上続く
悲しい出来事や環境の変化によって一時的に食欲が落ちることは自然な反応です。
しかし、食欲不振が2週間以上続いたり、頭痛や体のだるさといった症状が長引く場合、精神疾患が原因となっている可能性も考えられます。
まずは身体的な病気かどうかを確認するためにも、早めの受診が大切です。
心に現れる変化
2週間以上うつ状態が続いている
強いストレスを受けると一時的に気分が落ち込むのは正常な反応です。
しかし、憂うつな気持ちや無気力感が2週間以上続く場合は、うつ病など精神疾患のサインである可能性が高いといえます。
この状態を放置すると、日常生活に大きな支障をきたすことがあるため、受診を検討しましょう。
思考力・集中力の低下で日常生活に支障がある
精神疾患は「こころの病気」であり、その原因によっては思考力や集中力に影響を及ぼします。
仕事や勉強に支障が出るだけでなく、身近な人との会話や日常的な判断が難しくなることもあります。
もし「死にたい」といった深刻な言葉を周囲に口にするようであれば、すぐに医療機関を受診し、必要に応じて付き添ってあげることも大切です。
精神疾患の原因は複雑で、体の症状から始まることもあれば、心の変化としてあらわれることもあります。
症状を「疲れのせい」「気の持ちよう」と自己判断せず、早めに受診することが症状の悪化を防ぐ大切なポイントです。
精神疾患の相談ができる場所
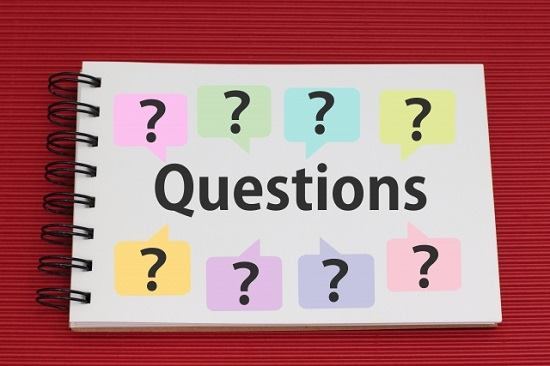
電話相談窓口
・よりそいホットライン
・こころの健康相談統一ダイヤル
SNS相談窓口
・こころのほっとチャット
・生きづらびっと
精神疾患の原因は人によって異なり、生活環境や性格、トラウマなどが複雑に絡み合うことで症状が出てきます。
そのため、「もしかしたら精神疾患かもしれない」と思ったときに、気軽に相談できる場所を知っておくことはとても大切です。
ここでは、医療機関以外でも利用できる主な相談窓口をご紹介します。
精神保健福祉センター
各都道府県や政令指定都市に設置されている精神保健福祉センターでは、精神疾患や心の不調に関する幅広い相談を受け付けています。
専門の相談員や保健師、精神保健福祉士などが対応し、必要に応じて医療機関や福祉サービスにつなげてもらえるのが特徴です。
「精神疾患の原因が何かわからないけれど、相談したい」といった場合にも安心して利用できます。
保健所・自治体の相談窓口
地域の保健所や自治体にも相談窓口が設けられています。
ここでは、受診先を探したいときや、家族の対応について知りたいときなど、日常生活に直結するサポートを受けられます。
電話や面談形式での相談が可能で、自治体によっては訪問支援を紹介してもらえることもあります。
自宅での暮らしに影響が出ている場合や、地域での支援を探している方にとって頼れる存在です。
電話やSNSでの相談先
「直接話すのはハードルが高い」と感じる方に向けて、電話やSNSで相談できる窓口も充実しています。
例えば、こころの健康相談統一ダイヤルや「よりそいホットライン」では、匿名で悩みを打ち明けることができます。
また、LINEやチャットを使ったSNS相談では、文字でやり取りできるため、気持ちを整理しながら相談できるのがメリットです。
これらの窓口は、緊急時の対応だけでなく、ちょっとした不安や疑問を相談するのにも役立ちます。
精神疾患の原因が明確でなくても、話を聞いてもらうことで安心感を得られるケースも多いため、一人で抱え込まず積極的に利用することをおすすめします。
精神疾患は「特別な人がなるもの」ではなく、誰にでも起こりうるものです。
原因を一人で突き止めようとするのではなく、まずは相談できる窓口にアクセスしてみましょう。
そこから必要な医療や福祉のサポートにつながる第一歩になります。
精神科訪問看護を利用するという選択肢

精神疾患の原因は人によって異なり、生活習慣や人間関係、遺伝や脳の働きなどさまざまな要因が複雑に絡み合っています。
そのため、治療やサポートも一律ではなく、一人ひとりの状況に合わせた支援が必要です。
その選択肢のひとつが「精神科訪問看護」です。通院が難しい方や、自宅で療養を続けたい方にとって心強いサービスとなります。
精神科訪問看護とは?
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得支援 ・症状のコントロール |
| 訪問日数 | 原則週3日以内(公的医療保険適用時) |
精神科訪問看護とは、看護師などの医療スタッフが自宅を訪問し、心の健康を支えるためのケアを提供するサービスです。
通院だけではカバーしきれない日常生活のサポートや、服薬管理、相談対応などを通じて、患者さんやご家族が安心して暮らせるよう支援します。
精神疾患の原因が複雑であっても、訪問看護では症状の変化を日常の中で把握し、早期の対応につなげることができます。
訪問看護で受けられるサポート内容
訪問看護では、以下のようなサポートを受けることができます。
- 症状の観察とコントロール
- 服薬の管理と副作用チェック
- 日常生活の援助(食事・睡眠・生活リズムの調整など)
- 人間関係や社会復帰に向けた相談
- ご家族への支援や不安解消
- 社会資源の活用支援
こうしたサポートは、精神疾患の原因となるストレスや孤独感を和らげ、再発予防にも役立ちます。
自宅に訪問してくれるスタッフと定期的に関わることで、安心感を得ながら生活を続けられる点も大きなメリットです。
料金の目安(保険や制度の適用も可能)
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
原則として週3回以内の訪問が可能ですが、必要に応じて柔軟に対応される場合もあります。
「通院だけでは不安」「家で安心して過ごしたい」という方にとって、精神科訪問看護は心身を支える大切なサービスです。
精神疾患の原因や症状が人によって違うからこそ、その人に合わせたサポートを受けることが再発予防や社会復帰の大きな一歩となります。
精神科訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
精神疾患はその原因が人によって大きく異なり、遺伝や脳の働き、性格やトラウマ、社会的な要因などが複雑に絡み合って発症します。
だからこそ、画一的な支援ではなく、その人に寄り添った支援が欠かせません。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科勤務経験のあるスタッフが中心となり、患者さんやご家族の状況に応じた柔軟なサポートを提供しています。
対象となる疾患は、うつ病・統合失調症・発達障害・PTSD・双極性障害など幅広く対応可能です。
日常生活の支援から服薬の管理、社会復帰へのステップまでトータルでサポートいたします。
ご本人だけでなく、ご家族の方へのサポートも重視しており、不安や悩みを一緒に解決していく体制を整えています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問は週1〜3回、1回あたり30分〜90分を基本としています。
祝日や土曜日の訪問にも対応しているため、ライフスタイルに合わせて柔軟に利用することができます。
また、状況によっては週4回以上の訪問も可能です。
シンプレ訪問看護ステーションで受けられるサポートは以下の通りです。
- 退院後の生活を支える退院支援
- 日常生活の安定を図る生活支援
- 再発を防ぐための予防的サポート
- 服薬管理や副作用チェック
- 社会復帰に向けた支援
- ご家族の方への相談やケア
また、医療処置にも対応可能で、胃ろうや自己導尿、カテーテル交換、ストーマ管理、在宅酸素療法、緩和ケアなども行っています。
看護とリハビリを組み合わせた支援により、患者さんが自分らしい生活を送れるよう力を尽くしています。
さらに、自立支援医療制度(精神通院)や心身障害者医療費助成制度、生活保護など、利用できる制度を活用しながら経済的負担を軽減できるように支援します。
介護保険を持っている方でも、精神科訪問看護は医療保険の対象となるため安心です。
精神疾患の原因や症状は一人ひとり異なりますが、シンプレはその多様性に対応できる体制を整えています。
ご本人やご家族が「一人では抱えきれない」と感じたとき、地域に根差した専門的なサポートを提供するのがシンプレ訪問看護ステーションです。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|精神疾患の原因を理解し、早めに相談を

精神疾患の原因は、遺伝や脳の働きといった生物学的要因、性格やトラウマなど心理的な要因、そして人間関係や社会環境といった社会的要因が複雑に絡み合って生じます。
つまり、「これだけが原因」と断定できるものではなく、さまざまな要素が積み重なって発症するのが精神疾患の特徴です。
そのため、症状の背景を理解することが治療や支援の第一歩になります。
また、精神疾患は特別な人だけが抱えるものではなく、誰にでも起こりうるものです。
体調の変化や心の不調が2週間以上続く場合、放置せずに医療機関へ相談することが大切です。
早めに相談することで、症状の悪化や再発を防ぎ、回復への道を早く進むことができます。
相談先としては、精神保健福祉センターや保健所などの公的窓口、電話やSNSの相談サービスなどがあります。
「受診するほどではないかも」と迷う場合でも、気軽に利用できる窓口があるため、一人で抱え込む必要はありません。
小さな不安の段階で声をあげることが、症状を深刻化させない大切な行動です。
さらに、通院や自宅療養に不安を感じる方にとっては、精神科訪問看護という選択肢もあります。
シンプレ訪問看護ステーションでは、うつ病や統合失調症、不安障害、発達障害など幅広い疾患に対応し、患者さんとご家族を包括的にサポートしています。
訪問看護では日常生活の支援や服薬管理、再発予防、社会復帰のサポートまでを提供し、安心して生活できる環境を整えることが可能です。
精神疾患の原因を知ることは、自分自身や大切な人のこころの不調を理解する手がかりになります。
そして、早めに相談し、適切な支援につなげることが回復への近道です。
もしもご本人やご家族が悩んでいる場合は、シンプレ訪問看護ステーションにご相談ください。
地域に根ざしたサポートで、安心できる生活を取り戻すお手伝いをいたします。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
精神疾患は誰にでも起こりうる病気であり、決して「気持ちの問題」や「甘え」ではありません。遺伝、脳の働き、性格、環境ストレスなど複数の要因が重なって発症するため、ご自身を責める必要はありません。
精神科・診療内科では、どんなことでもかまりませんので小さな悩みや心のわだかまりをお話いただくことが大事です。その上で薬物療法のみならず、気持ちの持ち方の具体的なアドバイスや環境調整など、医学的な診断をもとにい様々な視点からの対応を行います。
正確睡眠のトラブル、食欲不振、気分の落ち込み、集中力低下などの症状が2週間以上続く場合、あるいは生活に支障を感じる場合には我慢せずに精神科・心療内科への受診をお勧めします。
こころの悩みは一人で抱え込まず、「助けを求める力」を求めてください。
監修日:2025年11月5日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



