家族が精神疾患かもしれないときの対応と相談先|受診・訪問看護のポイント
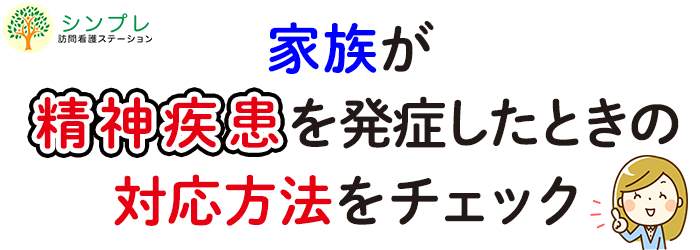
家族が精神疾患かもしれないと感じたとき、「どう対応したらよいのだろう」と不安になる方は少なくありません。
精神疾患は早期に気づいて適切な対応をとることで、症状の悪化を防ぎ、回復への道筋をつけやすくなります。
逆に、対応が遅れると症状が深刻化し、本人だけでなく家族全体の生活にも影響が及ぶことがあります。
この記事では、家族が精神疾患かもしれないときに最初に取るべきステップや、相談先・診療科の選び方、受診を勧める際のポイントなどをわかりやすく解説していきます。
「家族に精神疾患のサインがあるかもしれない」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。
家族が精神疾患かもしれないときの最初のステップ
精神疾患のサインに気づくことが大切
「気分の落ち込みが長く続いている」「眠れない日が増えた」「急に怒りっぽくなった」など、小さな変化に気づくことは家族にとってとても重要です。精神疾患は外から見ただけではわかりにくいため、普段から本人の言動や生活習慣を観察することが早期発見につながります。
また、幻覚や妄想のような強い症状が出ていなくても、日常生活に支障をきたす兆候があれば注意が必要です。本人が気づかないケースも多いため、家族のサポートが大きな役割を果たします。
早期相談・早期受診が重要な理由
精神疾患は早期に相談・受診することで適切な治療や支援につながりやすくなります。初期の段階であれば生活への影響も小さく抑えられ、回復のスピードも早まる可能性があります。
逆に放置してしまうと、症状が重症化し、仕事や学校など社会生活への影響が広がることもあります。家族が「少しおかしいかも」と感じた時点で専門機関に相談することが大切です。
まずは地域の保健所や精神保健福祉センターなどに相談し、必要に応じて精神科や心療内科の受診につなげていくのが良いでしょう。
家族が精神疾患かもしれないときの相談先は?
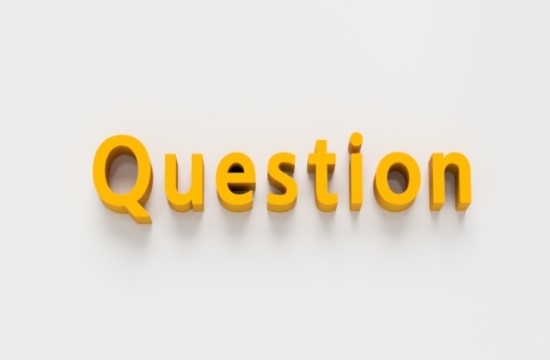
精神科・心療内科
家族が精神疾患を発症しているかもしれないと感じたとき、最初に検討したいのが医療機関での受診です。特に精神科や心療内科は心の不調を専門に扱っているため、診断と治療を受けることができます。
精神科ではうつ病や統合失調症、双極性障害など幅広い疾患に対応しています。一方、心療内科ではストレスによる不調や心身症など「体の症状と心の問題が関係しているケース」に強みがあります。
「病院に行くのは大げさかもしれない」と感じる方もいますが、早めに医師へ相談することが家族にとって最も安心できる一歩です。
保健所・精神保健福祉センター
公的な相談窓口として頼りになるのが、保健所や精神保健福祉センターです。これらの機関には医師・看護師・精神保健福祉士など専門職が在籍しており、地域の状況を踏まえたサポートを提供してくれます。
家族だけで抱え込むのではなく、地域の公的機関に相談することで、医療機関の紹介や福祉制度の案内など、実際的な支援につながります。特に「受診するかどうか迷っている段階」でも利用しやすい窓口です。
地域の相談窓口や支援センター
各自治体には、家族が精神疾患に悩んだときに相談できる支援センターや地域包括支援センターなどがあります。ここでは本人だけでなく、家族の不安やストレスについても相談可能です。
また、電話やSNSを通じて匿名で相談できる「いのちの電話」のような窓口もあります。費用は無料で、名前を伝える必要もないため、気軽に利用できる点が特徴です。
このような窓口を活用すれば、家族が孤立することなく安心して支援を受けられます。誰かに気持ちを聞いてもらうだけでも心が軽くなることがあるため、早めの相談が勧められます。
家族の精神疾患に関する相談で伝えるべきことは?

本人の生活状況や既往歴
家族が精神疾患の相談をする際には、本人の生活状況や既往歴を整理して伝えることが欠かせません。
生活状況としては、睡眠のリズムや食事習慣、日常生活で困っていること、依存傾向(アルコール・ギャンブルなど)の有無などが重要です。
また、過去にかかった病気や精神科での治療歴、現在服薬している薬の内容などもできる限りまとめておきましょう。特に入退院の有無や診断名は、医師や相談員が判断する際に大きな助けとなります。
こうした情報を準備しておくことで、相談がスムーズに進み、より適切な支援や治療につながります。
精神疾患を疑う症状や状況
次に、家族が「精神疾患かもしれない」と感じたきっかけや症状を具体的に伝えることが大切です。
たとえば「突然怒りっぽくなった」「部屋に閉じこもるようになった」「幻覚のような発言がある」など、客観的にわかる行動を整理しておきましょう。
文章にまとめるのが難しければ、日記や記録、写真・動画を残しておくのも有効です。実際の様子を専門家が確認できると、より正確に状況を把握できます。
症状が出た日付や時間帯を記録することで「どの時間帯に症状が強まるか」「周期性があるか」なども把握でき、診断の助けとなります。
どんな助けを求めているのか
最後に重要なのは、相談する側である家族が「どのような支援を望んでいるか」を具体的に伝えることです。
「服薬管理をサポートしてほしい」「社会復帰のための支援を受けたい」「家族の相談相手が欲しい」など、希望するサポート内容を整理して伝えましょう。
支援者側も「何を優先すべきか」を理解できるため、相談の質が高まり実際の支援につながりやすくなります。
特に公的機関では即時対応が難しいこともあるため、緊急性の有無や希望するサポートの優先度を伝えることが大切です。
精神疾患は本人だけでなく家族の生活にも影響するため、「家族も一緒に支えてほしい」という視点で相談することが望ましいでしょう。
精神疾患を扱っている診療科をチェック

精神科
| 診療科 | 精神科
|
|---|---|
| 扱っている 症状 |
・気分が落ち込む ・意欲が出ないなど |
| 治療対象 となる病名 |
・うつ病 ・双極性障害 ・パニック障害など |
精神科は、心の症状を専門に診断・治療する診療科です。
「落ち込みが続いている」「不安感が強い」「幻覚や妄想がある」などの症状がみられる場合は、まず精神科を受診するとよいでしょう。
早期に受診することで症状の悪化を防ぎ、適切な治療につながります。家族が精神疾患かもしれないと感じたら、ためらわず精神科に相談することが大切です。
心療内科
| 診療科 | 心療内科
|
|---|---|
| 扱っている 症状 |
・身体の検査で異常がないのに不調がある ・心と体のどちらが原因かわからない症状 |
| 治療対象 となる病名 |
・心身症 ・ストレス関連の体調不良など |
心療内科は、ストレスや心理的要因が体に影響を及ぼしていると考えられる症状に対応する診療科です。
「頭痛や腹痛が続くが検査では異常がない」「食欲が極端に落ちている」といった場合に役立ちます。
精神科との違いは明確ではなく、実際には心療内科でうつ病を診ることもあります。そのため、通いやすさや医師との相性を重視して選ぶのがおすすめです。
神経内科
| 診療科 | 神経内科
|
|---|---|
| 扱っている 症状 |
・もの忘れ ・体の動きの異常など |
| 治療対象 となる病名 |
・認知症 ・パーキンソン病など |
神経内科は、脳や脊髄、末梢神経、筋肉などに起因する症状を診る診療科です。
「体の震え」「歩行の不安定」「もの忘れが急に増えた」といった症状があるときに受診します。
精神疾患と直接の関連は薄いように見えますが、認知症など精神症状を伴う病気にも対応するため、高齢の家族の精神疾患を疑う場合には受診先の候補となります。
家族から本人に受診を説得するためのポイント

受診の必要性を繰り返し伝える
精神疾患の可能性がある場合、本人が自ら進んで受診するとは限りません。そのため家族が粘り強くサポートすることが重要です。
ただ「病院へ行こう」と言うだけでは拒否されてしまうこともあります。そこで症状を心配している気持ちを繰り返し伝えることが大切です。
例えば「最近眠れていないようだから心配」「専門家に相談したら安心できるかもしれない」と具体的に伝えることで、本人も受診を前向きに考えやすくなります。
また、初めて受診するときは家族が付き添うことで、安心感を与えることができます。
本人の訴えに耳を傾ける
本人が受診をためらう理由には「病気と思われたくない」「薬を飲みたくない」などさまざまな背景があります。
そのため、説得する前にまずは本人の言葉を丁寧に聞く姿勢が大切です。
話を遮らず、うなずきながら聞き返すことで「理解してもらえている」という安心感を持ってもらえます。
もし家族も感情的になってしまったら、少し時間を置いて冷静になってから話し合うことが望ましいでしょう。本人の気持ちを尊重する姿勢が、受診への第一歩となります。
心配していることを誠実に伝える
家族にとって一番大切なのは「本人のことを思っている」という気持ちを誠実に伝えることです。
「病院に行きなさい」では反発を招きますが、「あなたのことが大切だから心配している」と伝えることで、本人の心に届きやすくなります。
また、症状について話してくれた際には決して否定せず、共感しながら受け止めることが必要です。
本人は「自分を理解してくれている」と感じることで、治療を受けることに前向きになりやすくなります。家族が精神疾患に向き合う姿勢が、治療開始の大きな支えとなるのです。
精神疾患のある家族と接する際の注意点

正常な部分と病気の部分を区別する
精神疾患を抱える家族に接するとき、まず意識したいのは「病気の部分」と「その人自身の正常な部分」をしっかりと区別することです。
精神疾患は外から見えにくいことが多く、全てが病気に支配されているように思えてしまうかもしれません。ですが、本人の人格や得意なことは病気に奪われるわけではありません。
「病気だから仕方ない」と過干渉になるのではなく、できる部分は本人に任せ、支援が必要な部分だけをサポートしていくことが大切です。
本人の生活のしづらさを理解する
精神疾患を抱える人は、外見上は元気そうに見えても心の中で大きな負担を抱えています。
うつ病のように気分の落ち込みや意欲の低下が続くと、家事や仕事などの日常生活が大きな負担になることもあります。
家族が精神疾患を理解するためには、「なぜできないのか」ではなく「病気のせいで難しいことがある」と捉える視点が重要です。
その理解が、本人が安心して生活できる環境づくりにつながります。「家族が理解してくれている」と感じられることは、本人にとって大きな支えとなるでしょう。
本人ができることは自分でできるようサポートする
支援する側の家族は「助けたい」という気持ちから、つい何でも手を出してしまいがちです。しかし過度なサポートは本人の自立心を削いでしまうこともあります。
例えば、簡単な家事や身の回りのことなど、できることは本人に任せて見守ることが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることで自己肯定感が高まり、回復への意欲にもつながります。
精神疾患を抱える家族にとって、「できることを自分でできる環境」を作ることは社会復帰への大切なステップです。
精神科訪問看護を利用するという選択肢も

精神科訪問看護とは?
・精神科や心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けている方
・診断がなくても医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護師や准看護師
・作業療法士などリハビリの専門職
訪問時間
・1回あたり30分〜90分程度(医療保険適用)
精神科訪問看護とは、精神疾患を抱える方のご自宅を訪問し、生活や治療をサポートする仕組みです。
通院が難しい方や、日常生活に不安を抱える方にとって、自宅で専門職の支援を受けられることは大きな安心につながります。
また、本人だけでなく家族への助言や支援も行うため、「家族が精神疾患を抱えてどう支えたらいいかわからない」という状況にも心強いサポートになります。
精神科訪問看護のサポート内容
- 症状の観察や治療方針に関する相談
- 服薬管理や副作用のチェック
- 食事・睡眠など日常生活のサポート
- 社会参加や復職に向けたリハビリ支援
- ご家族への相談・助言
- 地域資源や制度の活用サポート
このように精神科訪問看護は多岐にわたるサポートを提供します。特に服薬管理や体調の観察は、病状の安定や再発防止に直結する大切な役割です。
また、家族にとっても「専門職が定期的に関わってくれる」という安心感があり、過度な負担を抱え込まずにすみます。
本人と家族の双方を支えるサービスであることが、精神科訪問看護の大きな特徴です。
精神疾患は長期的なケアが必要になることが多いため、訪問看護を利用することで地域で安心して暮らしながら治療を続けることができます。
精神科訪問看護ならシンプレ

シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しているステーションです。
ご自宅に専門スタッフが訪問し、服薬管理や生活支援、再発予防、社会復帰へのサポートなど幅広い支援を行います。
外出が難しい方や、家族が精神疾患を抱えてサポートに不安を感じているご家庭でも、自宅にいながら専門的な看護を受けられるのが大きな特徴です。
また、本人だけでなく家族の相談にも応じ、介護・看護負担を軽減する体制を整えています。
「病院と家庭の中間的な支え」として、安心して治療を続けられるようにサポートしています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
シンプレの訪問エリアは以下の地域を中心に展開しています。
- 東京23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市
- 埼玉県の一部地域
また、近隣の市区町村でも訪問できる場合があり、柔軟に対応可能です。
訪問は週1〜3回を基本としていますが、必要に応じて週4回以上の訪問も調整可能。祝日や土曜日も訪問しているため、家族の生活リズムに合わせて利用できる点も大きなメリットです。
1回の訪問時間は30分〜90分程度で、症状や状況に応じたサポートを行っています。
さらに、シンプレでは看護師・准看護師・作業療法士といった専門職が訪問。医療処置(胃ろう・カテーテル交換・褥瘡ケア・在宅酸素療法など)にも対応しています。
利用可能な制度としては「自立支援医療制度(精神通院)」「心身障害者医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「生活保護」があり、医療保険を活用して安心して利用できます。
精神疾患を抱える家族にとって、シンプレは心強いパートナーとなるでしょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

家族が精神疾患かもしれないときは早めの相談が大切
「家族が精神疾患かもしれない」と感じたとき、最も重要なのは早めの対応です。
気分の落ち込みや不眠、日常生活の変化など、小さなサインを見逃さずに専門機関へ相談することで、症状の悪化を防げます。
早期相談・早期受診は本人の回復だけでなく家族全体の安心につながるため、不安を抱え込まず積極的に行動してみましょう。
相談時は生活状況や症状を整理して伝えるとスムーズ
医師や相談員に話す際には、本人の生活状況や既往歴、気になる症状などを整理して伝えることが大切です。
「なぜ精神疾患を疑ったのか」「どんな支援を求めているのか」を具体的に伝えることで、支援内容もより適切なものとなります。
相談の場は家族が精神疾患と向き合う大切なきっかけになるため、事前準備をして臨むことがスムーズな支援につながります。
本人への接し方・受診の説得の工夫も重要
受診を勧める際には、強制するのではなく「心配している」という気持ちを誠実に伝えることが大切です。
また、本人の話に耳を傾け、気持ちを尊重することで受診や治療へのハードルが下がります。
精神疾患を抱える家族を支えるためには、「理解と寄り添い」が欠かせません。
訪問看護などの支援を利用して家族全体でサポートできる
精神疾患のケアは長期にわたることが多く、家族だけで支えるには限界があります。
そんなときに役立つのが精神科訪問看護です。専門職による定期的な支援を受けることで、本人の症状が安定し、家族の負担も軽減されます。
シンプレ訪問看護ステーションでは、本人の生活支援から家族へのサポートまで幅広く対応しているため、「一人で抱え込まず、支援を受けながら家族全体で回復を目指す」ことが可能です。
精神疾患に悩む家族は、まず一歩を踏み出して相談し、必要に応じて訪問看護などの制度を上手に活用しましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)






