訪問看護もできる小規模多機能型介護ホームとは?
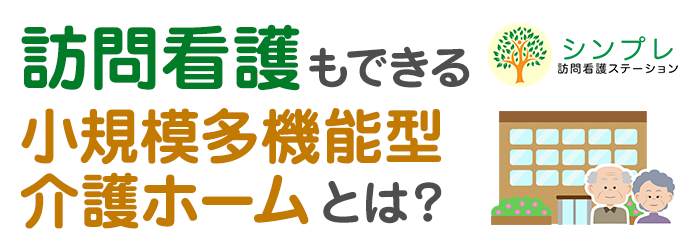
小規模多機能型居宅介護を検討しているけど、訪問看護サービスも同時に受けたい。
このような悩みを抱えている方のために生まれたのが、小規模多機能型居宅介護に訪問看護サービスを加えた看護小規模多機能型居宅介護です。
今回は、看護小規模多機能型居宅介護で受けることのできるサービスや利用方法などについて詳しく見ていきましょう
訪問看護もできる看護小規模多機能型居宅介護とは?

看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護とは、「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合わせたサービスです。
通い、泊まり、訪問介護、訪問看護のサービスを受けることができ、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため創設されました。
「病気があっても住み慣れた家で暮らしたい」「自宅で最期を看取りたい」と希望する方は多く、そのような方たちのために療養生活を支援します。
看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容
- 訪問看護サービス
- 介護サービス
- 宿泊サービス
- その他のサービス
看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容は幅広く、主治医と密に連携しながら様々な支援や調整を行います。
住み慣れた環境で必要な援助ができ、診療補助の内容に従って適切な経験や知識を持つ専門のスタッフが訪問・看護に対応します。
通院の負担を最小限に抑えながら専門的なケアが受けられ、通い・泊まり・介護・看護の4つの機能でご本人の状態や生活に合わせた利用が可能です。
看護小規模多機能型居宅介護の利用料の目安
13,493円
要介護2
18,879円
要介護3
26,539円
要介護4
30,100円
要介護5
34,047円
看護小規模多機能型居宅介護をご利用検討の方へ、1割負担の方の利用料金目安をご紹介します。
小規模多機能型居宅介護の利用料金は、ご利用者様の介護度によって異なります。
介護度とは、日常生活の自立度を点数化したもので、要介護1から要介護5までの5段階に分かれています。
上記料金の他に加算によって費用が加算される場合があります。
看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所
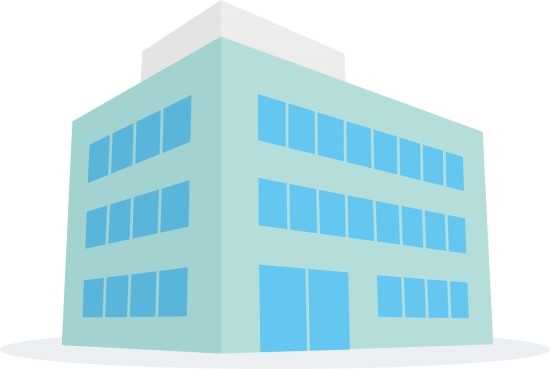
施設の利用定員は?
29名以下
通い定員
18名以下
宿泊定員
9名以下
看護小規模多機能型居宅介護の利用定員は、サービスを提供する施設全体で29名以下と定められています。
さらに、利用者が施設に通うサービスの利用定員は18名以下、宿泊サービスの利用定員は9名以下と、それぞれ制限を設けています。
これは、特に宿泊サービスは利用者様の安全確保に多くの職員を必要とすることから、適切な対応ができる範囲に利用人数を限定するためです。
利用者様が住み慣れた環境で療養生活を送ることを支援するだけでなく、職員の目が届きやすく、利用者様の体調変化にも気付きやすい少人数制ならではの利点も備えています。
人員の配置構成
通いサービス
利用者様3名に対して、介護職員1名以上が配置される
※うち1名は、看護師、保健師、または准看護師が配置されます。
訪問サービス
利用者様2名に対して、介護職員1名以上が配置される
※うち1名は、看護師、保健師、または准看護師が配置されます。
夜間のサービス
夜勤・宿直
1名以上のスタッフが配置される
人員基準は、おおむね小規模多機能型居宅介護(通所・宿泊・訪問介護)の基準に沿っています。
看護職員が通いや泊まりの利用時にも医療処置を行えるサービスなので、看護職員を手厚く配置する構成となっています。
医療度が高めの要介護者への対応力が高い看護小規模多機能型居宅介護ですが、事業所数はまだまだ少ないのが現状です。
人員・管理者基準
- 看護職員
- 介護支援専門員
- 管理者
日中は、通いの利用者3人に対して介護・看護職員が1人、訪問対応に1人が配置されます。
夜間は、泊まりと訪問対応で2人の職員が対応します(1人は宿直可)。介護支援専門員が1人配置され、ケアプランの作成や支援を行います。
本体事業所の管理者は、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した常勤・専従の者が務めます。
サテライト型事業所の管理者は、本体の管理者が兼務することができます。
看護小規模多機能型居宅介護のメリット

経済的負担が少ない
看護小規模多機能型居宅介護は利用料金が毎月定額制となっているため、介護費用が膨らみすぎる心配が少なく、経済的な負担を軽減できます。
利用には、お住まいの市区町村で「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定は、要介護状態や要支援状態にあるかどうかの程度判定を行うものです。
市区町村の窓口に申請すると、申請後に調査員が自宅を訪問し、認定が行われていきます。
柔軟な対応ができる
看護小規模多機能型居宅介護は通い・泊まり・訪問介護・訪問看護の4つのサービスを一つの事業所で提供する介護サービスです。
従来のサービスでは、それぞれのサービスを利用するために複数の事業所と契約する必要がありました。
しかし、看護小規模多機能型居宅介護ではすべて一つの事業所で完結するため、複数のサービスを組み合わせることで、利用者様のニーズに柔軟に対応することができます。
医療依存度の高い方でも利用することができる
看護小規模多機能型居宅介護は、医療度の高い方でも利用できるサービスです。
胃ろう、点滴、経管栄養、人工肛門などの医療的処置に対応しており、医療機器を常に使用している方でもご利用いただけます。
緊急時対応や看取りまで対応可能で、各種医療機器の管理やご家族への使用方法指導も行います。
看護小規模多機能型居宅介護の利用条件は?

事業所のある市区町村に住んでいること
- 事業所のある市区町村に住民票がある方
- 要介護1以上の認定を受けている方
看護小規模多機能型居宅介護を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
その条件の一つは、利用する事業所のある市区町村に住んでいることです。
利用可能な事業所があるかどうかは、お近くの保健所や保健センターなどに問い合わせをするといいでしょう。
要介護1以上の認定者であること
看護小規模多機能型居宅介護を利用するには、要介護1以上の認定を受けていることが必要です。
要介護認定とは、介護が必要な方の心身の状態を判定し、介護保険サービスの利用区分を決めるものです。
利用可能な事業所があるかどうかは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または、お近くの保健所や保健センターなどに問い合わせてください。
条件に当てはまらない場合は訪問看護という選択肢も
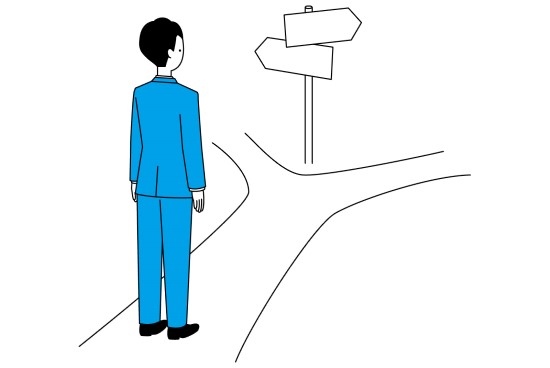
訪問看護サービスを提供している事業所
訪問看護ステーションは、全国に1万カ所以上あります。民間企業が運営しているところもあれば、病院や診療所が運営しているところもあります。
民間企業が運営している訪問看護ステーションは、地域のニーズに合わせて、さまざまなサービスを提供しています。
訪問看護に関する相談窓口は
地域包括支援センター、受診中の医療機関、またはお近くの訪問看護ステーションにご相談ください。
また、保健所・保健センターの保健師、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口にもご相談いただけます。
要支援または要介護の認定を受けている場合、ケアマネジャーが訪問看護をはじめ、ご本人やご家族の状況に応じたサービスをご提案いたします。
要介護認定を受けている方は、ケアマネジャーにご相談ください。
精神科訪問看護ならシンプレ看護ステーションへ!

シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しています。
医療機関や関係機関との架け橋となり、看護師や作業療法士などのスタッフがご自宅に定期的に訪問し、服薬の管理や健康状態の観察支援、ご家族への支援も行います。
ご家庭や地域社会で安心して日常生活を送ることができるよう、お手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
精神科訪問看護ってどんなことをしてくれるの?
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護の専門職
・リハビリテーションの専門職
訪問時間
・医療保険
(30分から90分程度)
精神科訪問看護は、精神疾患を抱える方が、ご自宅で安心して療養生活を送れるよう、看護師や作業療法士などの専門スタッフが訪問し、様々なサポートを行うサービスです。
対象となる方は精神科や心療内科に通院され、精神疾患と診断されている方、診断はなくても、睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された方です。
主治医に相談し、必要と判断された場合は、医療保険を利用して週3回まで訪問を受けることができます。
1回の訪問は30分から90分で、体調や病状に合わせて、訪問回数や時間を調整することができます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、基本的にリストに記載している地区で訪問看護の活動を行っています。
上記のエリア以外に自宅がある場合でも対応できる場合がありますので、まずはお気軽に電話や問い合わせフォームでお問い合わせください。
また、TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、あわせてぜひご覧ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

看護小規模多機能型居宅介護は、通い・泊まり・介護・看護の4つの機能でご本人の状態や生活に合わせた利用が可能です。
通院の負担を最小限に抑えながら専門的なケアが受けられますが、そこまでのサービスは必要ない、という方におすすめなのが「訪問看護サービス」です。
訪問看護サービスでも療養生活を送っている方の看護ができ、身体的・精神的なサポートを行えます。
シンプレ訪問看護ステーションでも精神科に特化した訪問看護サービスを提供しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



