訪問看護の特別指示書とは?有効期間・条件・通常指示書との違いを解説
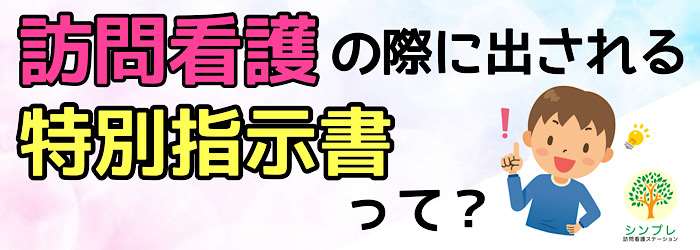

訪問看護を利用する際には、医師からの「指示書」が必要です。
その中でも医療保険の訪問看護で使用される特別指示書は、急な病状の悪化や在宅療養の安定を支えるために重要な役割を果たします。通常の指示書と比べて有効期間や訪問回数に違いがあるため、制度を正しく理解することが安心した療養生活につながります。
本記事では「訪問看護の特別指示書」について、仕組みや対象となるケース、通常の指示書との違いを詳しく解説します。訪問看護を検討中の方やご家族はぜひ参考にしてください。
特別指示書について詳しく紹介
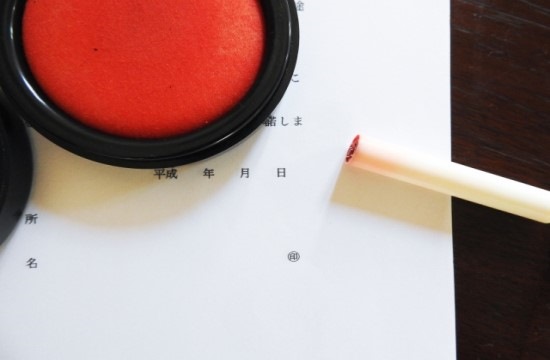
特別訪問看護指示書とは?
特別訪問看護指示書とは、医療保険の訪問看護で使用される指示書です。
主治医が患者さんの状態を診察し、頻繁な訪問看護が必要と判断した場合に交付される書類です。
通常の指示書では週3回までの訪問が基本ですが、特別指示書が交付されると週4日以上の訪問が可能になります。また、退院後3か月までは週5回まで訪問が可能です。
これは、急な容態変化や退院直後など、特に手厚いサポートが求められる状況で利用される重要な制度です。
特別指示書の有効期間はどれくらい?
- 最長14日間(1カ月あたり1回の交付が基本)
- 週4日以上の訪問が可能
通常の訪問看護指示書は最長6カ月間有効ですが、特別指示書は最長14日間と大幅に短いのが特徴です。短期間で集中的にサポートを受けられる仕組みで、在宅療養が安定するまでを支える役割を担っています。
どんなケースで特別指示書が発行されるのか
- 容態が急激に悪化したとき
- 末期がんなど終末期の患者さん
- 退院直後で毎日の確認が必要な場合
- 気管カニューレを使用している方(月2回交付可能)
- 深い褥瘡(じょくそう)がある方(月2回交付可能)
このように、特別訪問看護指示書は緊急性の高い状況や特別なケアが必要な場合に活用されます。医師の診断のもと、必要性が認められた場合のみ交付されるため、患者さんやご家族は安心して療養を続けられます。
通常の指示書と特別指示書の違いをチェック

訪問看護に必要な「指示書」とは?
訪問看護を受ける際には、主治医が作成する「訪問看護指示書」が必要です。この指示書には、どのような処置やサポートを行うかが記載され、看護師や作業療法士など訪問するスタッフは内容に基づいてケアを実施します。
指示書は、同じ診療科に属する医師であれば、主治医以外の医師が作成することも可能です。また複数の訪問看護ステーションを利用する場合は、それぞれのステーションに交付されます。つまり、訪問看護を受けるうえで欠かせない「指示書」が、サービスの基本的な土台となっているのです。
通常の指示書と特別指示書の違いをわかりやすく解説
通常の訪問看護指示書は、有効期間が1〜6カ月と比較的長く設定されています。
その一方で、訪問看護の特別指示書は緊急時や症状が不安定な時に交付される特別なものです。有効期間は最長14日間と短く、交付の条件も厳密に定められています。
また、通常の指示書では週3回までの訪問が基本ですが、特別指示書がある場合は週4日以上の訪問が可能です。これは、退院直後の安定が必要な方や急な容態悪化がある方など、集中的なケアが求められる状況に対応するための仕組みです。
さらに、条件を満たす場合には月2回までの交付も認められています。たとえば気管カニューレを使用している方や、深い褥瘡(じょくそう)がある方が該当します。
このように、通常の指示書と比べると、特別指示書は「より緊急性の高いケース」に備えた制度といえるでしょう。
訪問看護ではどんなサポートを受けられる?

- バイタルサインのチェック(血圧・脈拍・体温など)
- 食事・排泄・入浴などの日常生活の介助や指導
- 医師の指示による医療処置
- 服薬支援(残薬確認や服薬管理のサポート)
- ご家族への介護方法の助言・相談
- 症状緩和やターミナルケア
訪問看護は、在宅療養を行う方の生活と医療を支えるサービスです。
訪問するのは看護師や准看護師、作業療法士といった医療職であり、主治医の指示書に基づいたケアを行います。日常生活の補助から医療処置まで幅広い支援を受けられるのが特徴です。
特に、退院直後で体調が安定しない場合や、慢性疾患を抱えながら自宅療養を続けている方にとっては心強いサポートとなります。
また、特別指示書が交付されたケースでは、通常よりも訪問回数を増やし、集中的にサポートを受けられるため安心です。
利用者さんの年齢や病状に応じて支援内容は柔軟に対応されます。高齢の方や終末期の方には、穏やかに自分らしく過ごせるよう生活全体を支えるケアが行われ、若い方や回復を目指す方には、社会復帰を意識したリハビリや生活支援が充実しています。
ご家族に対しても介護や看護の相談を受けられるため、家庭全体で安心して療養を続けられる仕組みになっています。
精神科訪問看護で受けられる支援内容とは?

- 日常生活の維持やサポート
- 生活技能(料理・掃除・金銭管理など)の獲得・拡大
- 対人関係の維持や構築
- 家族関係の調整や支援
- 精神症状の悪化や再発の予防
- 医療機関や地域資源との連携
- 社会資源の活用支援
- 利用者さんのエンパワーメント
精神科訪問看護は、うつ病や統合失調症、アルコール依存症、PTSDなど精神疾患を抱える方を対象とした訪問看護です。
基本的なサポートは一般の訪問看護と同じですが、人との関わりや家庭内の調和を重視した支援が行われる点が特徴です。
例えば、精神疾患を持つ方は他者とのコミュニケーションが難しかったり、生活リズムを整えることが困難だったりします。
そのため、看護師は定期的な訪問を通じて、生活習慣の安定化や社会復帰を見据えた支援を行います。また、ご家族のサポートも重要で、介護や接し方に関する相談も受けられる仕組みです。
さらに、地域の医療機関や行政サービスと連携し、孤立を防ぐための「橋渡し」としての役割も果たしています。
精神科訪問看護は医療保険が適用されるため、特別指示書が必要となる場合には、主治医の判断に基づき緊急的な訪問回数の増加も可能です。これにより、急な症状の悪化や退院直後の不安定な時期にも安心してサポートを受けられます。
精神科訪問看護は、単なる医療支援にとどまらず「生活の質を高める」ための伴走支援です。
利用者さんが自分らしい生活を取り戻し、社会とのつながりを持てるようにする大切な役割を担っています。
精神科訪問看護を利用する主な疾患

統合失調症の方への支援
主な症状:妄想、幻覚、認知機能の低下
治療法:薬物療法、精神療法、生活支援
統合失調症はおよそ100人に1人が発症するといわれる精神疾患で、再発のリスクも高い病気です。
訪問看護では、服薬の管理や生活リズムの安定化を支援し、再発予防を目指します。必要に応じて特別指示書が交付され、頻回の訪問で集中的なサポートが行われることもあります。
うつ病・双極性障害の方への支援
主な症状:抑うつ状態、気分の浮き沈み、自尊心の低下、絶望感
治療法:薬物療法、心理的治療、カウンセリング
うつ病や双極性障害は、長期的に気分が変動し生活に支障をきたす疾患です。
訪問看護では、服薬のサポートや生活の立て直しを支援し、再発のリスクを軽減します。症状の悪化が見られる場合には、主治医と連携して特別指示書を活用し、週4日以上の訪問で状態の安定化を図ります。
アルコール依存症の方への支援
主な症状:飲酒のコントロール困難、離脱症状、不安や抑うつ
治療法:解毒治療、薬物療法、リハビリテーション
アルコール依存症は特効薬がなく、再発しやすい疾患です。
訪問看護では断酒の継続をサポートし、生活習慣の改善や再発防止に取り組みます。退院直後など不安定な時期には、特別指示書による集中的な訪問で安心した在宅療養を支えます。
PTSDの方への支援
主な症状:フラッシュバック、悪夢、回避行動、感情の麻痺、睡眠障害
治療法:曝露療法、認知行動療法、EMDR、薬物療法
PTSDは災害や事故、暴力など強いストレス体験によって発症します。訪問看護では、不安を軽減するための支援や生活の安定化をサポートします。状態が不安定で頻回の支援が必要な場合は、主治医の判断で特別指示書が発行されることもあり、短期集中的な訪問で症状の悪化を防ぎます。
精神科訪問看護の利用料金をチェック

精神科訪問看護の基本料金について
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
精神科訪問看護の料金は、訪問時間や自己負担割合によって変わります。医療保険が適用されるため、実際に支払うのは利用料の1〜3割です。例えば30分未満の訪問であれば数百円程度、60分未満でも数千円以内で利用できるケースがほとんどです。
「訪問看護は高額では?」と不安を感じる方もいますが、医療保険や各種助成制度が利用可能なため、安心して利用できる仕組みになっています。
さらに、必要に応じて特別指示書が交付される場合でも、制度の範囲内で利用できるので過度な経済的負担にはなりません。
訪問看護で適用される医療保険と制度
| 時間 | 30分未満 | 30分以上60分未満 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 467円 | 816円 |
| 2割負担 | 934円 | 1,632円 |
| 3割負担 | 1,401円 | 2,448円 |
訪問看護では、年齢や所得に応じて負担割合が異なります。一般的には以下のように区分されます。
- 6歳未満:2割負担
- 6〜70歳未満(現役世代):3割負担
- 70〜74歳:2割負担(一定所得以上の方は3割)
- 75歳以上:1割負担(一定所得以上の方は3割)
さらに、精神科訪問看護では「自立支援医療制度(精神通院)」や「心身障害者医療費助成制度」などの制度を活用できます。
これらを利用することで自己負担を軽減し、継続的な療養を安心して続けられるのが特徴です。
精神科訪問看護なら当ステーションにお任せください!

シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護を提供しています。
うつ病や統合失調症、双極性障害、依存症など幅広い疾患に対応し、患者さんが自分らしい生活を送れるよう支援しています。スタッフには精神科勤務経験のある看護師・准看護師・作業療法士が在籍しており、安心してご利用いただけます。
また、医療機関や行政、地域の関係機関と情報共有を行い、退院後の生活支援や社会復帰に向けたサポートも積極的に実施。必要に応じて特別指示書を主治医と連携して発行し、急な症状悪化や退院直後に集中的な訪問を行うことも可能です。
当ステーションが選ばれる理由
- 幅広い対応疾患:統合失調症、うつ病、双極性障害、依存症、PTSD、認知症など
- 経験豊富なスタッフ:精神科勤務経験を持つ看護師や作業療法士が在籍
- 柔軟な訪問体制:週1〜3回を基本に、必要に応じて週4回以上の訪問にも対応
- 安心のサポート:服薬支援、再発予防、生活支援、家族への助言も充実
- 利用しやすい制度:自立支援医療制度や医療費助成制度を活用可能
対応エリアは東京23区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、埼玉県一部です。近隣地域でも訪問できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|訪問看護の特別指示書を正しく理解して安心のサポートを

「訪問看護の特別指示書」は、急な容態の悪化や退院直後の不安定な時期など、特に手厚いサポートが必要な場面で交付される大切な制度です。
通常の訪問看護指示書と比べて有効期間が短く、訪問回数が多いのが特徴で、患者さんとご家族の安心につながります。
特別指示書を活用することで、週4日以上の訪問が可能になり、病状の安定や再発予防に役立ちます。
また、気管カニューレを使用している方や深い褥瘡がある方などは、月2回の交付が可能なケースもあります。これは、在宅での療養生活を支えるうえで非常に重要なサポートといえるでしょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、主治医と連携し、必要に応じて特別指示書を発行して集中的な訪問を行うこともあります。
精神疾患を含む幅広い疾患に対応し、生活支援や服薬管理、家族への支援まで総合的にサポートいたします。
在宅療養を安心して続けるためには、特別指示書の仕組みを理解しておくことが大切です。
精神科訪問看護を検討している方や、ご家族の介護で不安を抱えている方は、ぜひ当ステーションにご相談ください。地域に根ざしたサポートで、利用者さんとそのご家族をしっかりと支えます。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
訪問看護の特別指示書は、皆様の在宅療養を支える大切な制度です。退院直後や病状が不安定な時期に、通常より多くの訪問看護を受けられることで、安心して自宅での療養を続けることができます。
患者さんやご家族が安心して在宅生活を送れるよう、必要に応じて特別指示書を発行いたします。「こんなに頻繁に訪問してもらって申し訳ない」と遠慮される方もいらっしゃいますが、むしろ早期に集中的なサポートを受けることで、病状の悪化を防ぎ、安定した療養生活につながります。
精神疾患を含め、どのような病気でも、体と心、そして生活環境全体を見守ることが大切です。訪問看護スタッフと私たち医療者が連携し、皆様とご家族が笑顔で過ごせる毎日を支えてまいります。不安なことがあれば、いつでもご相談ください。一緒に乗り越えていきましょう。
監修日:2025年11月18日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (4)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



