身体表現性障害の治療法とは?症状・原因・対応方法をわかりやすく解説|シンプレ訪問看護ステーション
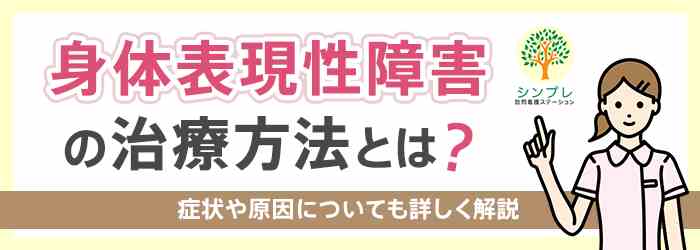
「身体表現性障害の治療」には、認知行動療法・森田療法・薬物療法など複数の選択肢があります。
元の内容を踏まえつつ、ここでは身体表現性障害の治療法や症状のポイントをわかりやすく整理します。
治療を検討中の方や、ご家族・支援者の方も、まずは基本を押さえて安心して一歩を踏み出しましょう。
身体表現性障害の治療法とは?

身体に問題がないことを理解することが第一歩
身体表現性障害の回復では、まず医学的な検査で重大な異常が見つからなかった事実を本人が受け止め、心理的な安心につなげることが欠かせません。
検査結果を疑い続ける行為そのものがストレスを高め、頭痛・めまい・吐き気などの不調をさらに強める悪循環を招きがちです。
「身体に大きな器質的問題はない」という認識を土台にして治療に取り組むことが、改善のスタートラインになります。こうした理解は「気のせい」と突き放すことではなく、症状が心身相関で生じうることを丁寧に説明し、不安を和らげるための大切なプロセスです。
加えて、ストレスや生活リズム、対人関係など日常要因を見直すことで、症状が強まるきっかけ(トリガー)と和らぐ要因(プロテクター)を整理しやすくなります。
身体表現性障害の治療では、こうした理解の共有が「検査を繰り返す→不安が増す→症状が増える」というループを断ち切る助けになります。
精神科で行われる身体表現性障害の治療法
精神科外来では、患者さんの状況や症状の強さに合わせて、心理療法と薬物療法を組み合わせながら「からだ」と「こころ」の両面にアプローチします。以下は代表的な方法です。
認知行動療法で思考のクセを改善する
日常でストレスを感じた場面を手がかりに、症状が悪化・軽快する要因を可視化し、非合理的な考え方のクセを修正していく心理療法です。
身体表現性障害の背景にある不安やとらわれを言語化し、行動実験などで「痛み=重大疾患」といった自動思考を柔らげ、症状への過度な注意を減らすことを目指します。
森田療法で不安や症状との付き合い方を学ぶ
不安や身体感覚を無理に追い払わず、あるがままに受けとめながら生活行動を整えていくアプローチです。
入院・外来・自助グループなど多様な場で実践され、症状にとらわれるほど苦痛が増すという悪循環を断つ手助けになります。
薬物療法で症状や併発疾患を和らげる
不安や抑うつの強さに応じて、抗不安薬や抗うつ薬などを検討します。背景にあるストレス反応を鎮め、こだわりや不安の高まりを緩和することで、心理療法への取り組みやすさを高めます。
痛みが前面に出る場合は、症状に応じた鎮痛・自律神経系への対応が行われることもあります。
身体表現性障害の症状について

代表的な症状とは?
身体表現性障害は、医学的な検査で異常が見つからないにもかかわらず身体的な不調が長期間続くことが特徴です。代表的な症状には、頭痛・腹痛・倦怠感・息苦しさ・しびれなどがあり、人によって現れる部位や強さは異なります。これらの症状は実際に感じられるものであり、「気のせい」や「思い込み」と片づけることは適切ではありません。
特に、ストレスや緊張が高まったときに症状が悪化しやすいという特徴があり、環境の変化や人間関係の不安などがきっかけとなることが多くあります。
身体表現性障害は「心の問題が身体に表れている状態」であり、心身の両面から丁寧に対応することが大切です。
症状ごとに分かれる5つのタイプ
身体表現性障害は、現れる症状や訴えの特徴によっていくつかのタイプに分類されます。それぞれの特徴を理解することで、適切な対応や治療方針を立てやすくなります。
身体化障害
身体のあちこちに複数の症状が現れ、長期にわたって続くタイプです。内臓や筋肉などに痛み・吐き気・めまいなどが現れますが、検査では明確な異常が確認できません。日常生活や仕事に支障をきたすこともあります。心身のストレスを身体が代わりに訴える形で症状が出るケースが多く見られます。
転換性障害
運動や感覚に関する異常が現れるタイプです。たとえば、手足が動かない・声が出ない・感覚が鈍いといった症状が一時的に出現します。神経系の検査では異常が見つからないにもかかわらず、本人には実際に症状が感じられるため、心理的な要因が強く関係していると考えられます。
身体醜形障害
自分の外見に対して強い違和感や劣等感を抱き、実際には問題がない部分を「欠点」だと感じ続けてしまう状態です。鏡を頻繁に確認したり、人前に出ることを避けたりといった行動につながります。美容整形を繰り返すケースもあり、自己イメージの変化が生活の質を大きく左右します。
疼痛性障害
慢性的な痛みが続くタイプで、医学的な原因が特定できないにもかかわらず痛みが強く現れます。痛みは一部位に限られる場合もあれば、全身に及ぶこともあります。痛みへの不安や恐怖が増すことで症状がさらに悪化することもあり、心理的サポートやリハビリテーションが効果的な場合があります。
心気症
軽い身体の違和感を「重大な病気ではないか」と強く心配し、繰り返し病院を受診してしまう状態です。検査で問題がないと説明されても安心できず、不安が続くのが特徴です。「病気への恐れ」が中心となるため、医療者との信頼関係づくりと心理的支援が重要になります。
身体表現性障害の原因とは?

身体表現性障害の原因はひとつではなく、心理的・社会的・生物学的な要因が複雑に絡み合って生じると考えられています。たとえば過去のトラウマ体験や強いストレス、完璧主義的な性格傾向などが背景にある場合も少なくありません。特に「人に迷惑をかけたくない」「我慢しなければならない」といった考え方が強い人ほど、心身のバランスを崩しやすい傾向があります。
心理的ストレスが長く続くと、自律神経やホルモンの働きが乱れ、頭痛・胃痛・めまい・動悸などの身体的症状が現れることがあります。この状態を「心身相関」と呼び、心の状態が身体に影響を与える代表的な例です。心と体は密接につながっており、心理的な負担が身体症状として現れることは珍しくありません。
家庭や職場での人間関係、過労、不安や抑うつ状態なども発症の引き金になり得ます。また、過去に病気を経験した人が「また同じ症状が出るのではないか」という強い不安を抱くことで、症状が再燃することもあります。これは、身体表現性障害が単なる「思い込み」ではなく、心理的要因が実際に身体の反応として現れる病態であることを示しています。
さらに、家族や周囲の反応も症状の持続に影響を与えることがあります。たとえば、「無理しないで休んで」と心配する言葉が、結果的に症状への意識を高めてしまうケースも見られます。適切な理解とサポートを得ることが、回復への第一歩です。
うつ病を併発する可能性があることに注意

身体表現性障害は、長引く身体症状によるストレスや不安が続くことで、うつ病を併発するリスクが高いことが知られています。症状が改善しない焦りや「自分のせいだ」といった罪悪感が積み重なり、気分の落ち込みや無気力感が強まるケースも少なくありません。
特に、「どうしても体の痛みや不快感が取れない」「検査で異常がないと言われても不安が消えない」といった状態が続くと、心のエネルギーが徐々に低下していきます。「何もする気が起きない」「以前のように楽しめない」と感じる場合は、うつ病の併発を疑うサインかもしれません。
うつ病を併発すると、身体表現性障害の症状もより強く感じやすくなるため、早めの対応が重要です。
身体症状が主であっても、心の不調を軽視せず、精神科や心療内科への相談を検討することをおすすめします。
また、うつ病との併発が見られる場合には、薬物療法と心理療法を並行して行うことが多く、抗うつ薬や抗不安薬によって気分を安定させながら、思考の偏りを修正していきます。症状の背景にある「無力感」や「自己否定感」に寄り添う治療が、心身の回復に向けた大切な一歩になります。
家族や周囲の理解も非常に重要です。「怠けている」「気の持ちよう」といった言葉は逆効果となり、症状を悪化させる要因になります。共感的に話を聞き、無理に励まさず寄り添う姿勢が、本人の安心感を支える大きな力となります。
身体表現性障害の方への接し方のポイント

身体表現性障害の方に接する際は、「症状を否定せず、共感的に寄り添う姿勢」が大切です。本人は実際に痛みや不調を感じており、「気のせい」や「大丈夫」といった言葉は、かえって孤立感を深めることにつながります。「つらい気持ちを理解しようとする態度」が、回復への大切な支えになります。
家族や支援者は、まず本人が感じている苦痛を受け止め、「無理をしなくていい」と安心できる環境を整えることが重要です。同時に、症状の話題ばかりに焦点を当てすぎず、生活や趣味など前向きな話題も取り入れることで、心のバランスを取り戻すサポートができます。
また、医療機関や訪問看護などの専門支援を早めに活用することも効果的です。身体表現性障害は一人で抱え込むほど症状が強まりやすいため、第三者の支援を得ながら、治療や生活の方向性を一緒に考えることが望まれます。
本人が「また痛みが出たらどうしよう」と不安を訴える場合は、否定せずに「その気持ちは自然なこと」と受け止めつつ、「どうすれば少し楽に過ごせるか」を一緒に考える姿勢を持つと良いでしょう。安心感と信頼関係が築かれることで、症状へのこだわりや恐怖が少しずつ和らいでいきます。
さらに、支援者自身の心の健康も大切です。家族が疲弊してしまうと、サポートの継続が難しくなります。時には専門家やカウンセラーに相談しながら、自分自身のストレスケアも行いましょう。
「支える側が安心して関われること」が、結果的に本人の安定にもつながります。
精神科訪問看護で受けられるサポート

精神科訪問看護とは?
精神科訪問看護とは、看護師や作業療法士などの医療専門職が自宅を訪問し、精神疾患を抱える方の生活や治療をサポートする医療サービスです。病院やクリニックへの通院が難しい方でも、自宅で必要な支援を受けられる点が特徴です。「安心して自宅で過ごせるように支える」ことを目的としています。
身体表現性障害の方は、通院や外出が不安になりやすく、治療の継続が難しい場合もあります。訪問看護を利用することで、定期的な見守りや心身のケアを受けながら、少しずつ生活リズムを整えていくことが目指すことができます。
身体表現性障害に対応する訪問看護の内容
精神科訪問看護では、身体表現性障害の方に対して以下のような支援を行います。
- 服薬状況の確認と服薬支援
- 不安や痛みなどの訴えへの傾聴とカウンセリング
- 生活リズムの調整や日常生活動作のサポート
- ストレス対処法やリラクゼーションの練習
- 家族への支援とコミュニケーション助言
こうした支援を通して、「症状にとらわれない生活」を目指すサポートを行います。特に、訪問看護師が定期的に訪れることで、孤立感が軽減され、再発予防にもつながります。
精神科訪問看護を利用するメリット
精神科訪問看護を利用することで、以下のようなメリットが得られます。
- 通院が難しい方でも自宅で治療を継続できる
- 症状や生活状況を定期的に見守ってもらえる安心感
- うつ病や不安障害などの併発疾患にも柔軟に対応
- 再発や入院のリスクを減らす予防的効果
看護師が心身の両面から支援することで、治療へのモチベーションを保ちやすくなるという点も大きな利点です。また、医師と連携して状態変化に早期対応できるため、安心して在宅生活を続けることができます。
精神科訪問看護の料金の目安
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
精神科訪問看護は、医療保険が適用されるサービスです。費用の自己負担は、利用者の所得や制度利用の有無によって変わります。一般的には1回あたり数百円〜千円台で利用できる場合が多く、経済的負担を抑えて継続的なサポートを受けられます。
また、「自立支援医療(精神通院医療)」制度を併用することで、自己負担が1割程度に軽減されるケースもあります。詳細は、各自治体や訪問看護ステーションに確認すると良いでしょう。
身体表現性障害の方が利用できる制度

自立支援医療(精神通院医療)で負担を軽減
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
自立支援医療制度は、精神疾患患者様が安心して治療に専念できるよう、心身の障害に対する医療費の自己負担額を1割まで減らす医療制度です。
状況によっては、睡眠剤から抗うつ薬までいくつかの種類の薬が出されるので、1回の通院の負担が大きいと感じた人も多いと思います。
自立支援医療を受けるためには、患者様の住んでいる役所へ申請する必要があり、申請してから受領証が届くまでに時間が掛かるので、早めに手続きをするのがよいでしょう。
自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神科・心療内科などでの治療にかかる医療費の自己負担を軽減できる公的制度です。身体表現性障害の治療で通院が長期化する場合、この制度を利用することで経済的な負担を大きく減らせます。
具体的には、医療保険が適用される範囲での自己負担が原則1割となり、薬代や訪問看護、カウンセリングなどの費用も対象になります。対象となるのは、精神疾患で継続的な通院・治療が必要と認められた方で、市区町村の福祉課を通じて申請します。
申請には、医師の診断書・保険証・マイナンバーなどが必要です。手続きにやや時間がかかる場合もあるため、早めに申請を行うことがポイントです。なお、所得状況によって自己負担上限額が設定されるため、低所得世帯ではより軽い負担で利用できることもあります。
精神障害者保健福祉手帳による支援
身体表現性障害で日常生活や社会生活に支障がある場合は、精神障害者保健福祉手帳の取得を検討するのも有効です。この手帳を持つことで、公共交通機関の割引や税金の控除、就労支援など、さまざまなサポートを受けることができます。
等級は障害の程度によって1〜3級に分かれ、申請には医師の診断書が必要です。手帳を取得することで、精神科訪問看護や福祉サービスの利用がスムーズになる場合もあります。自分に合った支援を受けるためにも、主治医やソーシャルワーカーに相談しながら手続きを進めると安心です。
また、状況に応じて「心身障害者医療費助成制度」や「生活保護制度」などの活用も可能です。身体表現性障害は長期的なサポートが必要な場合が多いため、制度を上手に利用して無理なく治療を続けることが回復への近道になります。
精神疾患のサポートならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレの特徴
シンプレ訪問看護ステーションでは、身体表現性障害をはじめとする多様な精神疾患に対応し、利用者一人ひとりに寄り添った支援を行っています。訪問は看護師・准看護師・作業療法士が担当し、心のケアと生活支援の両面から回復をサポートします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
対応エリアは、東京23区・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市・埼玉県一部です。近隣地域の方も相談可能で、週1〜3回(状況により週4回以上)まで訪問対応が可能です。祝日や土曜日も訪問を行っているため、働いている方やご家族の予定にも合わせやすい体制が整っています。
1回あたりの訪問時間は30〜90分で、服薬支援・生活支援・再発予防・社会復帰支援など、症状や目的に合わせた看護を行います。特に、身体表現性障害の方にはストレス緩和・不安軽減・生活リズムの改善を重視し、心身両面の安定を目指します。
さらに、胃ろう・自己導尿・カテーテル交換・褥瘡(じょくそう)ケアなど、医療的処置にも対応しており、在宅での安心な療養生活を支えることができます。医療保険制度の活用も可能で、自立支援医療制度や心身障害者医療費助成制度などの利用についてもご案内しています。
対応可能な精神疾患
シンプレ訪問看護ステーションでは、以下のような幅広い精神疾患に対応しています。
- うつ病・統合失調症・発達障害
- 知的障害・PTSD・双極性障害
- 不安障害・パニック障害・適応障害
- 薬物依存症・アルコール依存症
- 強迫性障害・自閉スペクトラム症・認知症 など
症状や疾患の重さに関係なく、「家で安心して暮らしたい」「社会復帰を目指したい」という想いに寄り添いながら支援しています。医療機関との連携も密に行い、主治医の指示のもとで看護計画を立てるため、安心してサービスを利用できます。
精神疾患の回復には「つながり」と「継続」が大切です。シンプレでは、利用者やご家族が前向きに日常を取り戻せるよう、経験豊富なスタッフがサポートします。ご相談は無料で受け付けており、初めて訪問看護を利用される方も安心してお問い合わせいただけます。
まとめ|身体表現性障害の治療は早期対応と支援が重要

身体表現性障害は、検査で異常が見つからなくても実際に身体のつらさを感じる心身の病気です。痛みや不調を「気のせい」と片づけず、心理的な要因を理解しながら適切に治療していくことが大切です。
治療では、認知行動療法・森田療法・薬物療法などを組み合わせて行うケースが多く、「症状と上手に付き合いながら回復を目指す」という視点が重要です。本人の努力だけでなく、家族や医療者の理解・協力があってこそ、安定した生活を取り戻すことを目指すことができます。
うつ病や不安障害を併発することもあるため、早めの相談と治療の継続がポイントです。体調の変化が続くときは、心療内科・精神科での受診や、訪問看護などの専門支援を活用してみましょう。
特に、シンプレ訪問看護ステーションのような精神科訪問看護では、在宅での心身ケアや再発予防、服薬支援などを受けながら、少しずつ生活のリズムを整えていくことが可能です。医療保険制度の利用で経済的負担を抑えながら、安心してサポートを受けられます。
身体表現性障害の治療は、長期的な視点で取り組むことが大切です。焦らず、自分のペースで「回復への一歩」を積み重ねていきましょう。シンプレでは、利用者とご家族の想いに寄り添う支援を心がけています。まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



