ギャンブル依存症の症状とは?特徴・併発しやすい精神疾患・治療法を解説
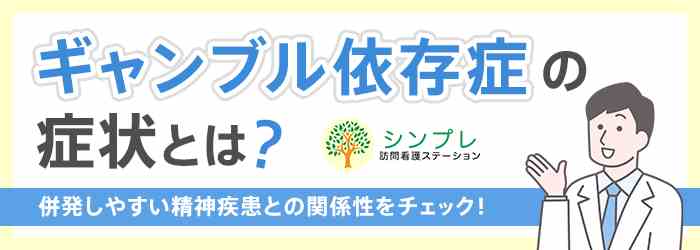
ギャンブル依存症の症状は、単なる「遊び」を超えて、お金や時間を過剰にギャンブルへ費やしてしまうことから始まります。
次第に生活の中心がギャンブルになり、仕事・家庭・人間関係にまで悪影響を及ぼすようになります。
また、ギャンブル依存症は精神疾患との関係も深いことが知られており、うつ病や不安障害などを併発するケースも少なくありません。
適切な理解と治療が必要な「病気」であり、早期の気づきとサポートが大切です。
この記事では、ギャンブル依存症の症状や特徴、併発しやすい疾患、治療法、相談先などを詳しく解説します。
ギャンブル依存症の症状とは?
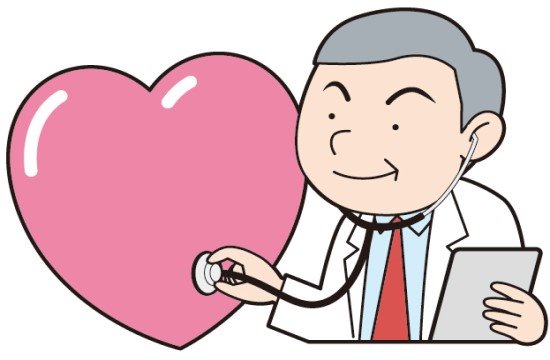
お金や時間をギャンブルに使いすぎる
ギャンブル依存症では、パチンコ・競馬・オンラインカジノなどにのめり込み、生活費や貯金をギャンブルにつぎ込むようになります。
最初は「少しだけ」と思っていても、次第に歯止めが効かなくなり、借金にまで発展するケースもあります。お金と時間をコントロールできない状態が続くことは、依存症の初期サインといえるでしょう。
生活や人間関係に支障をきたす
ギャンブルに時間を取られることで、仕事の遅刻や欠勤、家庭内の不和など日常生活への支障が生じます。
家族や友人との関係が悪化し、孤立感が強まることもあります。このような状態が長く続くと、社会生活全体に影響を及ぼす深刻な問題へと発展します。
借金・隠し事・嘘が増える
負けた分を取り戻そうとする「負け追い」が始まると、さらに深みにはまり、借金や金銭トラブルが増えていきます。
また、家族や友人に隠れてギャンブルを続けるために嘘をつくようになり、信頼関係が壊れていくことも少なくありません。
やめたいのにやめられない強い衝動
「もうやめよう」と思っても、頭の中でギャンブルのことが離れず、再び手を出してしまう。この強い衝動がギャンブル依存症の代表的な症状です。
米国精神医学会のDSM-5でも、こうした衝動性やコントロールの欠如が診断基準に含まれています。放置すると精神的な負担が大きくなり、うつ状態や不安障害を併発する場合もあります。
ギャンブル依存症は意志の弱さではなく、治療が必要な「病気」です。少しでも思い当たる症状がある場合は、早めに専門機関へ相談しましょう。
ギャンブル依存症の患者数と現状
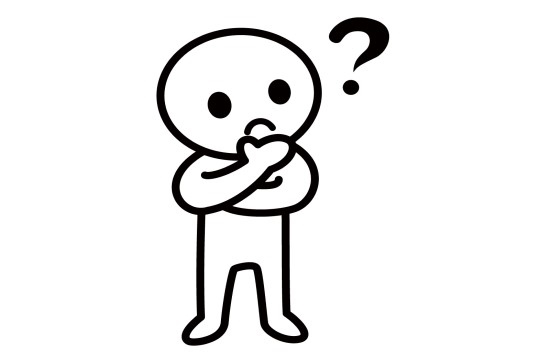
日本におけるギャンブル依存症の推定患者数
近年、日本ではギャンブル依存症が社会問題として注目されています。
厚生労働科学研究による調査では、成人の約4.8%がギャンブル依存の疑いがあると推計されており、これはおよそ約500万人規模に相当します。
つまり、20人に1人がギャンブル依存症の症状を抱えている可能性があるという深刻な数字です。
依存症と診断されるまでには個人差がありますが、共通して見られる傾向は、ギャンブルへの強い執着と生活への悪影響です。
これは単なる趣味の範囲を超えて、仕事や家庭に支障をきたすケースが多いのが特徴です。
また、日本の特徴として、パチンコ・スロット・競馬・競艇・宝くじなど、多様なギャンブルが身近に存在しており、気軽に利用できる環境が依存を助長しているともいわれています。
こうした背景が、ギャンブル依存症の患者数を増やす要因のひとつになっているのです。
海外と比較した日本の依存率の高さ
海外の研究では、ギャンブル依存症の有病率は一般的に0.4〜2.0%前後とされています。これに対して日本の推定4.8%という数字は、他国と比べても高い水準です。
つまり、日本ではギャンブル依存症が特に発生しやすい社会的・文化的土壌があるといえるでしょう。
たとえば、欧米諸国ではカジノやオンラインベッティングが厳しく規制されている一方で、日本では「遊技」としてのグレーゾーンが存在します。
そのため、依存症が発症しても気づきにくく、治療や相談につながりにくい傾向がみられます。
このように、日本のギャンブル依存症は、潜在的な患者数が非常に多いにもかかわらず、支援を受けられていない人が多いという現状があります。
ギャンブル依存症の症状を放置すると、経済的困窮・家族関係の破綻・うつ症状などを引き起こすおそれがあるため、早期発見と治療が重要です。
ギャンブル依存症と併存しやすい精神疾患

うつ病との併存リスク
ギャンブル依存症の方の多くは、長期間のストレスや罪悪感、経済的な不安からうつ病を併発するケースが少なくありません。
負けが続くと自己否定感が強まり、「自分はダメだ」「もう立ち直れない」と感じてしまうことがあります。こうした思考が慢性化すると、うつ状態に移行しやすくなります。
また、うつ症状が強いと判断力が低下し、再びギャンブルに逃げてしまう悪循環に陥ることもあります。
つまり、ギャンブル依存症と抑うつ状態は相互に影響し合う関係にあるのです。回復のためには、どちらか一方ではなく、心身両面へのアプローチが欠かせません。
アルコール依存症との併発
ギャンブル依存症は、アルコール依存症との併発も非常に多いといわれています。
ギャンブルの興奮や不安を紛らわすために飲酒量が増え、やがてお酒なしではいられない状態に陥るケースです。
お酒によって判断力が鈍り、再びギャンブルをしてしまうという負のスパイラルが起こります。
このようなケースでは、ギャンブル依存症の症状とアルコール依存の双方に対応できる医療機関や専門支援が必要です。
依存が重なることで、生活の立て直しがより困難になるため、早めの治療開始が重要です。
不安障害や衝動性障害との関係
ギャンブル依存症は、不安障害や衝動性障害との関係も深いとされています。ギャンブルをしているときに一時的に不安や緊張が和らぐように感じることが、依存行動を強化してしまうのです。
また、もともと衝動を抑えることが苦手な人は、ギャンブルでの刺激を強く求めやすくなります。
このような併存疾患がある場合、単なる意志や根性だけで克服するのは難しいのが現実です。
医師やカウンセラーなどの専門家による治療を通じて、心の不安定さを整え、衝動をコントロールする力を養うことが求められます。
ギャンブル依存症と精神疾患の併存は珍しくなく、実際には複数の問題が絡み合っていることが多いです。
精神的なサポートを受けながら治療を進めることで、回復への道が大きく開けるでしょう。
ギャンブル依存症かもしれないと思ったら

ご家族にとって大切なこと(寄り添い・見守り・相談)
- 家族だけで問題を抱え込まない
- 気になったら早めに専門機関へ相談する
- 本人を責めず、冷静に話を聞く姿勢を持つ
- 家族向けの自助グループを活用する
- 借金や金銭問題には直接関わらない
ギャンブル依存症の治療には、本人の努力だけでなく家族の支えが不可欠です。とはいえ、ギャンブルによる問題が続くと、怒りや失望の気持ちが生まれてしまうのも自然なことです。
しかし、感情的に責めてしまうと、本人はますます閉じこもってしまい、症状が悪化する可能性があります。
大切なのは、「本人を理解しよう」という姿勢で寄り添うことです。
家族が正しい知識を持つことで、依存症を「意志の弱さ」ではなく「治療が必要な病気」として捉えられるようになります。専門機関への相談や家族向け支援グループの参加は、問題解決への第一歩となるでしょう。
ご本人様にとって大切なこと(受診・相談・回復の第一歩)
- ギャンブルを思い出す環境を避ける
- 小さな成功体験を積み重ねる
- 信頼できる人に相談する
- 自助グループに参加して支え合う
「やめたいのにやめられない」――これは多くの方が抱えるギャンブル依存症の症状です。
決して恥ずかしいことではなく、誰にでも起こり得る心の病気です。ギャンブルに対する衝動は、本人の意思だけで抑えるのは難しい場合があります。
そのため、医療機関や相談窓口で専門的なサポートを受けることが大切です。
また、同じ悩みを抱える仲間と交流できる自助グループへの参加も効果的です。体験を共有しながら回復のプロセスを支え合うことで、「一人ではない」と感じられます。
専門家や家族と連携しながら、少しずつ依存の連鎖を断ち切ることが回復への近道です。
「自分はまだ大丈夫」と思っていても、ギャンブルに関する嘘や借金が増えてきたら要注意です。気づいた時点で行動することが、取り返しのつかない事態を防ぐ最善の方法です。
ギャンブル依存症の治療方法

認知行動療法による思考・行動の修正
ギャンブル依存症の治療において中心的な役割を果たすのが「認知行動療法(CBT)」です。
これは、ギャンブルに走ってしまう原因となる考え方や行動のクセを見直し、より現実的で健全な思考パターンへと修正していく治療法です。
たとえば「次こそ勝てる」「ギャンブルでしかストレスを解消できない」といった非現実的な思い込みは、依存を強化する要因です。
認知行動療法では、こうした誤った認知を客観的に捉え直し、感情のコントロールやストレス対処の方法を身につけていきます。
この治療は時間をかけて継続的に行うことが重要で、カウンセラーや心理士との対話を通じて、ギャンブル以外のストレス解消法を見つけることが目標です。
自分の感情と向き合いながら、再発を防ぐための「心のリハビリ」を行うプロセスとも言えます。
薬物療法による衝動性のコントロール
ギャンブル依存症では、うつ病や不安障害など他の精神疾患を併発している場合が多く見られます。
そのため、症状によっては薬物療法が併用されることがあります。抗不安薬や抗うつ薬、睡眠導入剤などが処方され、気分の安定や衝動性のコントロールを助けます。
薬物療法の目的は、ギャンブルに走ってしまう衝動を抑えることではなく、精神的なバランスを整え、依存を引き起こす心理的背景を軽減することにあります。
ギャンブル依存症の症状は人によって異なるため、医師が状態を見極めながら最適な治療を組み合わせていきます。
また、認知行動療法と薬物療法を併用することで、より効果的に再発を防ぐことが可能になります。
焦らず、段階的に回復を目指すことが何よりも大切です。
ギャンブル依存症の治療は、「意思の強さ」で解決するものではなく、専門的な支援と継続的な治療によって回復していくものです。
症状に気づいた段階で専門機関へ相談し、早期に治療を始めることが回復への第一歩です。
ギャンブル依存症の相談窓口

地域の保健センターでの相談
ギャンブル依存症で悩んでいる方やご家族は、まずお住まいの地域にある保健センターに相談してみましょう。
保健センターでは、精神保健福祉士や看護師などの専門職が常駐しており、依存症に関する相談や医療機関の紹介を行っています。
「誰に相談すればいいのか分からない」と感じている方も、保健センターなら安心して初めの一歩を踏み出せます。
電話や面談での相談が可能で、必要に応じてカウンセリングや支援機関につなげてくれます。
ギャンブル依存症の症状が軽いうちに相談すれば、早期の治療介入が可能になります。
孤立せず、地域のサポートを活用することが回復への近道です。
精神障害者保健福祉手帳の利用
ギャンブル依存症を含む精神疾患のある方は、「精神障害者保健福祉手帳」を利用できる場合があります。
この手帳は、精神的な不調が長期間続き、日常生活や社会生活に制限がある方を支援する制度です。
手帳は1級〜3級に分かれており、等級に応じて税金の控除、公共料金の割引、公営住宅の優先入居、交通機関の割引など、さまざまな支援が受けられます。
申請には、医師の診断書と申請書類を市区町村の窓口に提出します。
ギャンブル依存症の症状によって生活に支障をきたしている場合、この手帳の利用を検討することで、経済的・社会的な負担を軽減することができます。
公的制度を上手に活用することも、回復を支える大切な一歩です。
自助グループ(ギャンブラーズ・アノニマスなど)
自助グループとは、同じ悩みを持つ人同士が集まり、体験を共有しながら支え合う場です。
ギャンブル依存症では「ギャンブラーズ・アノニマス(GA)」が代表的で、全国各地で定期的にミーティングが行われています。
自助グループでは、互いの体験を話し合うことで孤独感が和らぎ、「自分だけじゃない」と感じることができます。回復へのモチベーションを維持するための心の支えにもなります。
また、家族向けの「ギャマノン(Gam-Anon)」というグループもあり、依存症者を支える家族が悩みを共有しながら学び合うことができます。
ギャンブル依存症は一人で抱え込むと悪化しやすいため、こうした場を積極的に利用することが大切です。
精神科訪問看護という選択肢も

精神科訪問看護とは?基本を解説
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護師・准看護師
・作業療法士などのリハビリ専門職
訪問時間
・週1〜3回(1回あたり30〜90分程度)
精神科訪問看護とは、看護師などの医療専門職がご自宅を訪問し、心の病を抱える方の生活を支援するサービスです。
外出が難しい方や通院の負担を減らしたい方にとって、非常に有効な支援手段となります。
特にギャンブル依存症を抱える方の場合、通院が継続できない・生活リズムが乱れやすいなどの課題があり、訪問によるサポートが回復への大きな助けになります。
ギャンブル依存症における訪問看護の支援内容
・規則正しい生活リズムの調整
・金銭管理や家族関係のサポート
服薬・健康管理
・服薬の確認や副作用の観察
・体調変化や心理面のチェック
社会復帰支援
・主治医・関係機関との連携
・社会復帰に向けたリハビリ
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
精神科訪問看護では、患者さんの生活をトータルで支援します。
ギャンブル依存症の方に対しては、ギャンブルに頼らない生活づくりのサポートや、再発を防ぐための見守りが中心です。本人だけでなく家族にも寄り添い、安心して生活できるよう支援を行います。
精神科訪問看護のメリット(自宅で支援を受けられる)
訪問看護の最大のメリットは、自宅にいながら専門的な支援を受けられる点です。
通院が難しい方や、外出に不安を感じる方でも安心してケアを継続できます。また、訪問スタッフが日常生活を見守ることで、症状の悪化を早期に察知できるのも大きな利点です。
さらに、家族へのアドバイスや相談対応も行われるため、家庭全体の安心感にもつながります。ギャンブル依存症の回復には、本人だけでなく周囲の支援体制を整えることが重要です。
精神科訪問看護の料金と自己負担
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
精神科訪問看護は医療保険が適用されるため、自己負担は原則1〜3割です。
訪問回数や時間、利用する制度によって負担額が変わりますが、他の医療サービスに比べて経済的な負担が軽いのが特徴です。
自立支援医療(精神通院医療)で負担を軽減
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた月額自己負担上限額です。
精神科訪問看護を利用する場合、「自立支援医療制度(精神通院)」を活用すれば、医療費の自己負担を1割に抑えることが可能です。
経済的な負担を軽減しながら、継続的に支援を受けることができます。
精神疾患をお持ちならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、うつ病・統合失調症・発達障害などの精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しています。
看護師や作業療法士などの専門職がご自宅を訪問し、利用者様が安心して日常生活を送れるよう、医療面・生活面の両方から支援を行います。
ギャンブル依存症を抱える方に対しても、精神面の安定を保ちながら再発を防ぐサポートを実施。ご本人だけでなく、ご家族にも寄り添い、負担を軽減できるよう努めています。
また、シンプレでは医療機関・福祉サービス・地域支援センターなどと密に連携を取りながら、利用者様一人ひとりに合わせた看護プランを作成。
急な体調変化にも対応できる体制を整え、安心して在宅で療養できる環境を支えます。
対応している精神疾患一覧
- ギャンブル依存症
- うつ病
- 統合失調症
- 発達障害(ASD・ADHDなど)
- 双極性障害
- 不安障害・パニック障害
- アルコール依存症
- 薬物依存症
- 強迫性障害・PTSD
上記のように、シンプレ訪問看護ステーションでは幅広い精神疾患に対応しています。
特にギャンブル依存症は、うつ病や不安障害などの併発が多い傾向にあり、総合的な支援体制が不可欠です。医療面だけでなく、生活全体の安定を見守ることが回復への近道です。
シンプレの対応エリア
シンプレ訪問看護ステーションでは、以下のエリアで訪問サービスを行っています。
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
※近隣の市区町村の場合も訪問可能な場合がありますのでご相談ください。
訪問回数は週1〜3回を基本に、状態や主治医の指示に応じて柔軟に調整可能です。土曜・祝日にも対応しており、利用者様の生活リズムに合わせてサポートを行っています。
「病院に通うのがつらい」「家族に負担をかけたくない」などのお悩みをお持ちの方は、ぜひシンプレ訪問看護ステーションへご相談ください。
あなたの心と生活を支えるパートナーとして、全力でサポートいたします。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|ギャンブル依存症の症状に早めに気づき相談を

ギャンブル依存症は、「勝てば取り戻せる」「次こそ大丈夫」といった思い込みから抜け出せず、生活のあらゆる場面に悪影響を及ぼす病気です。
本人が気づかないうちに進行することも多く、気づいたときには経済的・精神的な負担が大きくなっているケースも少なくありません。
ギャンブル依存症の症状は、金銭的な問題だけでなく、家族関係や仕事・社会生活にも深く関わります。
「やめたいのにやめられない」「嘘をついてまでギャンブルを続けてしまう」などの行動が見られた場合は、依存のサインと考え、早めの相談が重要です。
依存症は意志の弱さではなく、治療と支援が必要な「病気」です。医療機関や地域の保健センター、自助グループ、精神科訪問看護など、回復を支えるための選択肢はたくさんあります。
どんな形でも良いので、まずは一歩を踏み出してみましょう。
また、ギャンブル依存症はうつ病や不安障害などを併発することも多く、総合的なサポートが不可欠です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、こうした精神疾患をお持ちの方に対し、自宅で安心して療養できるように支援を行っています。ご本人だけでなく、ご家族も含めた支援を大切にしています。
もし、身近な人やご自身に当てはまると感じたら、迷わず専門機関へご相談ください。早期に気づき、治療や支援を受けることが回復への第一歩です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化した専門チームが、あなたの生活と心の安定を全力でサポートします。
ギャンブル依存症の克服には時間がかかる場合もありますが、諦める必要はありません。正しい知識と支援を得ることで、再び自分らしい生活を取り戻すことができます。悩みを一人で抱え込まず、まずは相談から始めてみましょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



