知的障害の症状と特徴を解説|原因・診断基準・支援方法まとめ
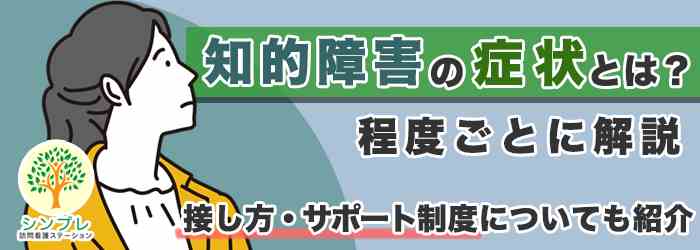

知的障害の症状は、人によって現れ方が異なり、学習面やコミュニケーション能力、日常生活の自立度合いに大きな差があります。
読み書きが難しい、意思をうまく伝えられないなどの特徴が見られることもあれば、生活のほとんどに支援が必要な場合もあります。この記事では、知的障害の症状の特徴を軽度・中等度・重度・最重度の4つの段階に分けて解説します。さらに原因や診断基準、接し方のポイント、利用できる制度や支援についても紹介し、適切なサポートにつなげるための情報をまとめました。
知的障害の症状の現れ方を理解しよう
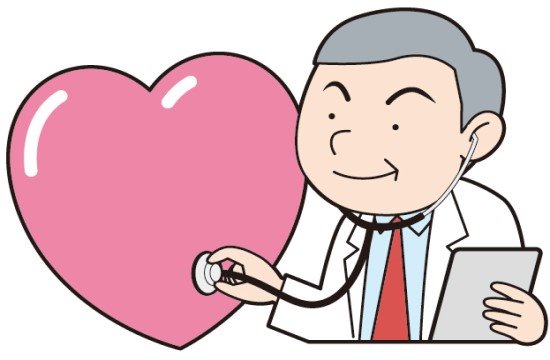
知的障害はIQの数値や発達の度合いに応じて大きく4つの段階に分けられます。それぞれの段階で症状の現れ方や日常生活への影響が異なり、必要となる支援の内容も変わってきます。
まずは、軽度・中等度・重度・最重度の特徴を知ることで、理解を深め、支援方法を考えるきっかけになります。
軽度知的障害の特徴
- ・IQ50〜69の範囲
- ・読み書きや計算が苦手
軽度知的障害はIQが50〜69の範囲にある方を指します。
学校の授業内容の理解や文字の読み書きに困難を感じることが多く、同年代の子どもと比べて学習面で遅れが目立ちます。
社会的には友人関係を築くことができますが、相手に流されやすく、悪影響を受けやすい点が課題です。また、発達障害やうつ病などの二次障害を併発するケースもあります。
中等度知的障害の特徴
- ・IQ35〜49の範囲
- ・言語や運動能力の発達に遅れ
中等度知的障害の方は、言葉の理解や表現に遅れがみられ、会話に限界がある場合が多いです。
運動能力の発達も遅く、勉強に関しては簡単な内容までで限界が訪れることがあります。ただし、人との関わりを好み、簡単な社会活動には参加できるため、支援を受けながら地域で生活していくことは可能です。
完全な自立は難しい場合が多いですが、環境の工夫やサポートで生活の幅が広がります。
重度知的障害の特徴
- ・IQ20〜34の範囲
- ・日常生活に広範な支援が必要
重度知的障害の方は、読み書きや数の概念が身につきにくく、時間や金銭の理解も難しい場合が多いです。
食事や入浴、排泄といった基本的な生活動作に介助が必要であり、運動障害や神経系の問題を併発することも少なくありません。
周囲からの継続的なサポートが不可欠であり、家族や支援者の負担が大きくなる傾向があります。
最重度知的障害の特徴
- ・IQ20未満
- ・身支度や生活すべてに支援が必要
最重度知的障害はIQ20未満で、ほとんどの場合、他者の支援がなければ生活を送ることができません。
てんかんや視覚・聴覚の障害を伴うこともあり、意思疎通は身振りや表情など非言語的手段に限られることが多いです。
しかし、リハビリや適切なサポートを受けることで、自分の意思を少しずつ表現できるようになる可能性もあります。ごく簡単な作業や家事に参加できるケースもあり、適切な支援の重要性が強調されます。
知的障害の原因と患者数の割合

知的障害の主な原因
知的障害が生じる原因はひとつではなく、遺伝や染色体異常、胎児期の感染症、出産時のトラブルなど多岐にわたります。
多くの場合、胎児期や幼少期の発達段階で障害が明らかになることが多いですが、成長とともに徐々に症状が表面化し、学習や生活の困難さを通じて気づかれるケースもあります。
知的障害の症状はこのような要因の組み合わせによって現れ方が異なり、一人ひとりに合わせた支援が求められます。
原因を正しく理解することは、家族が支援方法を考えるうえで非常に大切です。
たとえば、遺伝的要因が関与している場合には、専門の医師による継続的なフォローが必要となりますし、出産時のトラブルが背景にある場合には、リハビリや生活支援が中心となることもあります。
ですが、知的障害の約30〜40%は原因が特定できません。原因が分からなくても、適切な支援により生活の質を高めることは十分可能です。適切な医療的サポートにつなげることが、その後の生活の質に大きく影響するのです。
知的障害のある方の人数と発症割合
厚生労働省の調査(平成28年)によると、国内における知的障害者の数は約108万人と推計されています。
年齢別では18歳未満が約22%、18〜65歳が約60%、65歳以上が約15%となっています。
過去の調査と比較すると患者数は増加傾向にあり、社会全体での理解と支援体制の強化が求められています。
また、男女別にみると65歳未満では男性の割合が約6割を占めており、女性よりも男性に多い傾向が示されています。
このデータからも、知的障害は決して珍しいものではなく、社会全体として取り組むべき課題であることが分かります。さらに地域ごとに支援資源の差があるため、利用できる制度やサービスについて情報を得ておくことが重要です。
知的障害の症状は軽度から最重度まで幅があり、それぞれに応じた支援の在り方が求められます。患者数の統計を理解することは、家族や支援者にとって具体的な支援を検討する出発点となるでしょう。今後も正確なデータを把握しながら、一人ひとりに合わせたケアや地域での支え合いを広げていくことが大切です。
知的障害の診断基準について

- 出生前検査
- 知能および発達評価
- 中枢神経系の画像検査
- 遺伝学的検査
知的障害の診断には、複数の検査や評価方法が組み合わせて用いられます。
代表的な方法は「知能および発達の評価」で、標準化された知能検査を行い、平均値と比較して知的能力がどの程度下回っているかを確認します。
また、知的障害の診断はIQの数値だけでなく、日常生活における適応能力(コミュニケーション、セルフケア、社会性など)を総合的に評価して行われます。同じIQ値でも、適応能力によって必要な支援は大きく異なります。
これらの評価を踏まえて、知的障害の症状がどの段階に分類されるのかを判断する目安となります。ただし検査結果は一度で確定するものではなく、生活状況や行動の特徴と併せて総合的に評価されることが重要です。
なお、知的障害は、発達期(通常18歳未満)に発症したものを指します。
成人後の事故や病気による認知機能低下は知的障害とは区別されます。
さらに、出生前検査では胎児の段階で染色体異常や先天的な異常を確認できることもあります。
画像検査では脳の状態を調べ、中枢神経系に異常がないかをチェックします。加えて、遺伝学的検査により、家族歴や遺伝的要因がどのように影響しているのかを明らかにすることが可能です。
診断の際に大切なのは、症状の程度を正しく把握するだけでなく、その人が日常生活でどのような困難を抱えているのかを丁寧に評価することです。
たとえば、知能指数が同じであっても、家庭や学校での支援体制、環境要因によって生活のしやすさは大きく異なります。そのため、単に数値で判断するのではなく、本人の発達の背景や生活全体を考慮することが不可欠です。
また、知的障害の診断は一度きりで終わるものではなく、成長とともに見直される場合があります。幼少期には発達の遅れが目立たなくても、学齢期に入ると学習面での困難が顕在化することもあります。そのため、継続的な観察と専門医による定期的な評価が望まれます。
このように、知的障害の診断基準は単に検査結果だけでなく、本人の行動や生活の様子、家族の意見など多角的な視点から判断されます。診断を通じて正しく理解することで、その後の支援や利用できる制度につなげやすくなるのです。
知的障害の方との接し方のポイント

・ゆっくり、やさしく必ず本人に話しかける
・話が長くならないよう具体的にはっきり伝える
・本人の年齢に応じた接し方を心がける
・できることを認め、失敗を責めない(成功体験を積み重ねる)
してはいけないこと
・子ども扱いしない(年齢相応の尊厳を保つ)
・本人を無視して周囲だけで話す
・「頑張れば普通になれる」といった励まし
知的障害のある方と接する際には、症状の程度や生活状況に応じた配慮が欠かせません。
軽度の場合は自立して生活できる部分も多いですが、重度や最重度になると日常生活のほとんどで支援が必要になります。どの段階であっても、相手を一人の人格として尊重し、安心してコミュニケーションできる環境を整えることが大切です。
まず、会話では難しい表現を避け、短く具体的な言葉で伝えるようにします。
知的障害の症状がある方は、抽象的な説明や長い話を理解することが難しい場合が多いため、シンプルに分かりやすく伝える工夫が必要です。また、指示やお願いごとをする際には、目を見て、落ち着いた声で話しかけることが信頼関係の構築につながります。
次に大切なのは、相手のペースや意思を尊重することです。
理解に時間がかかる場合も多いため、急かさず待つ姿勢が必要です。表情やしぐさを見て、本人の気持ちを読み取ることも効果的です。
たとえ言葉で返事ができなくても、身振り手ぶりで意思を伝えようとしている場合があるため、それを汲み取ることが支援の第一歩となります。
また、本人の年齢に合った接し方も意識しましょう。大人であっても、言葉や理解のレベルは子どもに近い場合があります。
しかし、その一方で大人としての尊厳を持っています。支援する側の「手助けしてあげる」という一方的な姿勢ではなく、共に生活を支えるパートナーとして接することが、本人の自信や安心感につながります。
さらに、家庭や学校、地域社会など周囲の人々が一貫した対応をすることも重要です。
異なる場面で接し方に差があると本人が混乱しやすくなるため、支援者同士で共通のルールや声かけ方法を共有しておくと良いでしょう。
知的障害の方と関わるすべての人が理解を深めることで、安心できる生活環境をつくることができます。
知的障害に悩んだときの相談やサポート

相談窓口の活用方法
- 保健センター
- 児童相談センター
- 心身障害者福祉センター
- 発達障害者支援センター
知的障害のある方やそのご家族が困ったときには、公的な相談窓口を利用することが大きな助けになります。
保健センターでは、医師や保健師が生活や健康に関する相談に応じてくれ、必要に応じて医療機関や支援サービスを紹介してくれます。児童相談センターでは、18歳未満の子どもの発達や家庭での対応について幅広く相談でき、子どもに合った支援プランを一緒に考えることが可能です。
また、心身障害者福祉センターでは、就労や生活に関するアドバイスを受けられるほか、発達障害者支援センターでは、知的障害と併せて発達障害をもつ方への専門的な支援が提供されます。
知的障害の症状が人によって異なるように、必要となる支援も一人ひとり違います。相談窓口を積極的に利用することで、本人に合った支援策を見つけやすくなります。
こうした窓口は無料で利用できる場合が多く、地域の社会資源をつなぐ役割を果たしています。ご家族だけで悩みを抱え込まず、早めに専門機関へ相談することが安心につながります。
子どもの場合に受けられる支援サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
知的障害のある子どもには、成長に合わせた福祉サービスを活用することができます。
児童発達支援は未就学児を対象に、日常生活に必要な動作や集団生活に慣れるための訓練を行うサービスです。医療型と福祉型があり、子どもの特性に応じて選択できます。
一方、放課後等デイサービスは、学校に通う子どもが放課後や長期休暇に利用できるサービスで、学習や生活のサポート、居場所づくりの役割を担っています。これらの支援を活用することで、子どもが安心して成長できる環境が整えられるのです。
さらに、地域によっては親の負担を軽減するためのレスパイトケア(家族の休息支援)が行われている場合もあります。知的障害をもつお子さんを育てる家庭は、日々大きなエネルギーを必要とします。外部の支援を取り入れることで家族全体の安心感を高め、より良い生活リズムを築くことが可能です。
知的障害のある方への支援は、本人だけでなく家族を含めたサポートが大切です。困ったときには一人で抱え込まず、相談窓口や地域の福祉サービスを利用して、より安心できる暮らしにつなげていきましょう。
大人が利用できる支援サービス

- ハローワーク
- 就労移行支援事業所
知的障害のある大人の方は、就労や生活の場面で困難に直面することが多くあります。
読み書きや計算が難しい、意思疎通に時間がかかるといった症状のために、就職活動や職場での適応に課題を抱えるケースも少なくありません。こうした状況を支えるために、公的なサービスや福祉制度を利用することができます。
まず代表的なのが「ハローワーク」での支援です。ハローワークでは、障害のある方を対象とした専門の相談窓口を設けており、就職活動に関するアドバイスや求人情報の提供を行っています。
場合によっては、担当者が採用面接に同行してくれることもあり、安心して活動できるようサポートが整えられています。
次に、「就労移行支援事業所」があります。これは障害福祉サービスの一つで、職業訓練やビジネスマナーの習得、履歴書の作成支援などを通して一般就労を目指すためのサービスです。
事業所に通うことで、日々の生活リズムを整えながら、仕事に必要なスキルを身につけることが可能です。特に就労移行支援は、働く意欲があるものの環境やサポートが不足している方にとって、社会参加への大きな一歩となります。
また、地域によってはグループホームや生活介護事業所など、日常生活をサポートする施設も利用できます。
知的障害の程度が重い方の場合、自立した生活が難しいケースもありますが、福祉サービスを活用することで安心して地域で暮らしていくことが可能です。こうしたサービスは、本人だけでなくご家族にとっても負担を軽減する重要な支援となります。
大人になってからも、知的障害のある方が自分らしく生活し、社会に参加できるようにするためには、こうした支援サービスを積極的に活用することが不可欠です。
本人の希望や特性に合わせて、どのサービスが適しているかを専門家と一緒に検討することで、より安心した生活につながります。
知的障害の方が利用できる制度
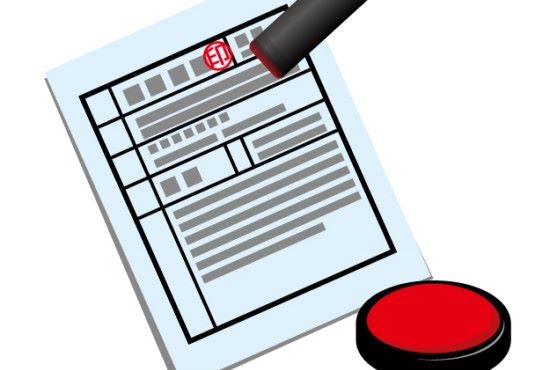
療育手帳について
療育手帳は、知的障害があると判定された方に交付される手帳で、各自治体の判定機関で審査を受けたうえで発行されます。
手帳を持つことで、障害福祉サービスや交通機関の割引、税制上の優遇など、日常生活を支えるさまざまな支援を受けることが可能です。
判定基準は自治体によって異なりますが、知的障害の症状の程度に応じて「軽度」「中度」「重度」に区分されるのが一般的です。更新の際には、改めて知能検査や生活状況の評価を受ける必要があります。
療育手帳を取得することで、学校や福祉施設での支援体制が整いやすくなり、本人や家族の負担を軽減できるという大きなメリットがあります。
特に進学や就職などライフステージが変化する時期には、支援の幅を広げるための重要な役割を果たすといえるでしょう。
自立支援医療制度(精神通院)で受けられる支援
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得1 | 2,500円 |
| 低所得2 | 5,000円 |
| 中間所得1 | 5,000円 |
| 中間所得2 | 10,000円 |
| 一定所得以上 | 20,000円 |
表は所得に応じた月額自己負担の上限額を示しています。
自立支援医療制度(精神通院)は、精神科や心療内科などに継続的に通院する方の経済的負担を軽減するための制度です。
この制度を利用すると、医療費の自己負担が1割に軽減され、さらに月額での上限が設定されます。そのため、長期にわたる治療や支援が必要な方にとって、大きな助けとなります。
特に、知的障害のある方は、併存する精神疾患に対して薬物療法や精神科訪問看護を利用するケースが少なくありません。
こうした支援も自立支援医療制度の対象に含まれるため、生活の質を維持しやすくなります。経済的な不安を減らし、継続的に必要な医療やサポートを受けられることは、本人や家族にとって大きな安心材料です。
制度を正しく理解し、申請を行うことで受けられる支援の幅が広がります。療育手帳と併用することで、教育・医療・福祉の各分野でより充実したサポートを受けられるようになりますので、ぜひ地域の福祉課や医療機関に相談してみてください。
在宅支援に役立つ精神科訪問看護という選択肢

精神科訪問看護とは?
・精神疾患の診断を受けた方
・精神科・心療内科に通院中の方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護師
・作業療法士などリハビリの専門職
訪問時間
・1回30分〜90分程度(週1〜3回が目安)
精神科訪問看護とは、看護師や作業療法士などの専門職がご自宅を訪問し、病気や障害の状態に応じたケアを行うサービスです。
通院だけではフォローしきれない生活面のサポートを受けられることが大きな特徴です。
特に知的障害のある方は、症状によって服薬管理や生活リズムの維持が難しい場合があり、訪問看護の支援によって安定した暮らしを続けられるようになります。
精神科訪問看護では、主治医の指示に基づき、服薬確認や健康チェック、生活リズムの調整支援を行います。
また、本人だけでなく家族への助言や相談にも対応しており、家庭全体を支える役割を果たします。「病院と家庭をつなぐ架け橋」としての役割を担うことが、訪問看護の大きな強みです。
精神科訪問看護を利用するメリット
- 自宅で安心して専門的なケアが受けられる
- 主治医と連携しながら生活を支援してもらえる
- 家族の負担を軽減できる
- 地域生活の継続をサポートしてくれる
自宅にいながら医療的な支援が受けられるため、外出や通院が難しい方にとって大きな安心感があります。また、定期的に訪問を受けることで、生活習慣の乱れや健康状態の変化にいち早く気づくことができ、早期の対応につなげられます。
さらに、訪問看護はご本人だけでなく、支えているご家族にとっても心強い存在です。ケアの方法や接し方について相談できるため、家族の心理的負担を減らし、安心して介護や支援を続けられるようになります。こうしたサポートは、家庭全体の生活の質を向上させる効果があります。
精神科訪問看護は、地域で暮らしながら必要なケアを受けられる仕組みを提供する大切なサービスです。
特に知的障害をはじめとする精神疾患を抱える方にとって、日常生活を支え、自立や社会参加を後押しするための有効な選択肢となります。
精神疾患や知的障害の支援ならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患や知的障害をお持ちの方に特化した訪問看護サービスを提供しています。
ご自宅に訪問し、安心して地域で暮らし続けられるよう生活支援や医療的サポートを行っています。
訪問するのは看護師、准看護師、作業療法士などの専門職で、主治医と連携しながら一人ひとりに合わせたケアを実施します。知的障害の症状に応じた支援も可能で、生活の中で困っていることを一緒に解決していける体制が整っています。
また、週1〜3回を基本に、1回30分〜90分の訪問を行っていますが、状況によっては週4回以上の訪問も対応可能です。
祝日や土曜日も訪問を行っているため、利用者やご家族の生活スタイルに柔軟に合わせることができます。「日常の中で安心して過ごせる環境づくり」を第一に考えた支援がシンプレの特徴です。
シンプレで対象となる精神疾患と支援内容
- 知的障害
- うつ病・統合失調症
- 発達障害・自閉スペクトラム症
- 双極性障害・不安障害
- PTSD・パニック障害
- 薬物依存症・アルコール依存症
- 認知症 など
シンプレ訪問看護ステーションでは、知的障害をはじめとする幅広い精神疾患に対応しています。
支援内容は服薬管理、生活支援、再発予防、社会復帰サポート、家族への助言など多岐にわたります。特に、日常生活での困難を和らげるための実践的な支援に力を入れており、利用者が安心して生活を続けられるよう丁寧にサポートします。
対応エリアは東京都23区を中心に、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、東久留米市、さらに埼玉県の一部地域にも訪問可能です。近隣市区町村についても相談に応じており、幅広いエリアをカバーしています。
さらに、胃ろうや自己導尿、在宅酸素療法、緩和ケアといった医療処置にも対応しているため、医療ニーズの高い方でも利用可能です。こうした体制により、在宅生活を続けたいと望む方やご家族を力強く支援しています。
知的障害や精神疾患により、生活や将来に不安を抱えている方も少なくありません。シンプレ訪問看護ステーションでは、そうした不安に寄り添いながら、安心できる地域生活の実現をサポートしています。お困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|知的障害の症状を理解し、適切な支援につなげよう

ここまで、知的障害の症状や原因、診断基準、接し方、そして利用できる支援制度やサービスについて解説してきました。
知的障害は軽度から最重度まで幅広い段階があり、知的障害の症状の現れ方は人によって大きく異なります。そのため、一人ひとりに合わせた柔軟な支援が必要です。
軽度の場合は学習やコミュニケーションに困難を抱えやすく、重度や最重度では日常生活の多くに支援が欠かせません。
重要なのは「症状の程度を理解したうえで、その人に必要な支援を選択すること」です。正しく理解することで、本人の自立を促し、家族や周囲の方々にとっても安心できる生活環境を整えられます。
また、知的障害を持つ方やご家族が孤立しないためには、相談窓口や地域の支援サービスを活用することが欠かせません。
児童発達支援や就労移行支援、精神科訪問看護といったサービスは、生活の質を高め、社会とのつながりを保つための大きな力になります。さらに、療育手帳や自立支援医療制度といった制度を利用することで、経済的負担を軽減し、継続的なケアを受けやすくなります。
シンプレ訪問看護ステーションでも、知的障害をはじめとする幅広い精神疾患に対応しており、服薬支援や再発予防、家族支援など多面的なサポートを行っています。地域に根ざした専門的なケアを通じて、安心できる生活を実現できるよう努めています。
知的障害のある方とそのご家族が、少しでも安心して暮らせるよう、まずは専門機関や支援サービスに相談してみてください。
適切な支援を受けることで、本人らしい生活を続けられる可能性が大きく広がります。困難を一人で抱え込まず、支援につながる第一歩を踏み出すことが、より良い未来を築くための大切なきっかけとなるでしょう。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
知的障害は病気ではなく、一人ひとりの個性の現れ方の違いです。学習や生活面で困難があっても、得意なことや好きなことがあり、適切な支援があれば地域で自分らしく生活することができます。
また、「できること」に目を向けることです。周囲の理解と適切なサポートにより、社会参加や就労の可能性は大きく広がります。ご本人のペースを尊重しながら、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。
ご家族の皆様へ。一人で抱え込まず、地域の相談窓口や福祉サービスを積極的に活用してください。療育手帳や自立支援制度など、利用できる制度も多くあります。
また、ご家族自身の休息も大切です。私たち医療者や支援者は、ご本人とご家族が安心して生活できるよう、チーム全体でサポートいたします。困ったときは遠慮なくご相談ください。
監修日:2025年11月28日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



