軽度知的障害とは?|特徴・診断・支援と相談窓口を解説
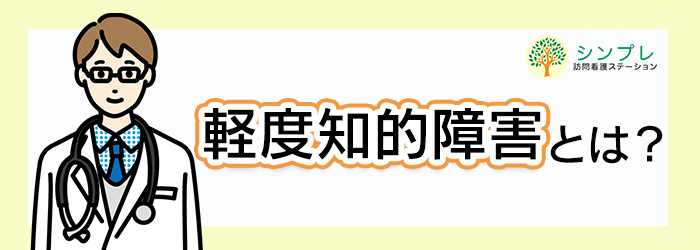

軽度知的障害は、知的障害全体の中でも多くを占める程度でありながら、外見や日常の様子だけでは気づかれにくいケースが少なくありません。
そのため、幼少期には障害が見過ごされ、大人になってから学習面や人間関係、就労などで生きづらさを感じる 方もいます。
この記事では、軽度知的障害の特徴や日常生活への影響、診断や支援の方法についてわかりやすく解説します。さらに、相談窓口や精神科訪問看護といったサポートの選択肢についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
軽度知的障害とは?

軽度知的障害は、知的障害の中でも比較的軽度な発達の遅れを示す状態で、IQはおおよそ50〜69の範囲に該当します。
判断が難しいため、最終的な診断には専門医の評価が必要です。ここでは、軽度知的障害の特徴について詳しく解説します。
知的機能と適応行動が平均よりやや低い
知的障害はIQや生活能力の程度によって重度から軽度まで区分されます。
軽度知的障害の方は、一般的な発達より少し遅れが見られるものの、日常生活や社会参加に大きな制約がない場合も多いです。そのため障害に気づかれないまま成長し、社会人になってから困難に直面するケースもあります。
言語や学習の理解に困難がある
軽度知的障害の方は抽象的な概念の理解が苦手で、小学校高学年以降の教科学習に遅れを感じやすい傾向があります。
ただし、日常生活に必要な動作は自立して行えることが多く、適切な支援を受ければ就労や社会生活を営むことが可能です。子どもの発達に疑問を感じた場合は、小児科などの専門機関に相談するとよいでしょう。
基本的な生活の能力を身につけることができる
軽度知的障害があっても、時間をかければ身の回りのことや生活スキルを習得できます。就労や自立を実現している方も多く、外部のサポートを活用することで安定した生活を送ることが可能です。
周囲がその人の特性を理解し、適切に支援することが生活の質を高める鍵となります。
中等度・重度との違い
中等度や重度の知的障害に比べると、軽度知的障害は学習や抽象的思考に難しさがあるものの、基本的な生活や簡単な職業に従事できる点が大きな違いです。
このため、早期に適切な支援を受けることで、自立した生活を目指すことができます。
軽度知的障害の特徴と日常生活への影響
軽度知的障害は日常生活に大きな支障が出にくいため、外見や会話だけでは障害があると気づかれにくい場合があります。
しかし、学習や人間関係、社会生活の中で特有の困難が生じやすく、本人や周囲に影響を及ぼすことがあります。ここでは具体的にどのような特徴が見られるのかを解説します。
学習面で見られる特徴
軽度知的障害のある方は、記憶や理解力に弱さがあり、学校教育の内容についていくのが難しいことがあります。
特に抽象的な概念や数学的思考を伴う課題は理解しづらく、繰り返し学習を行わなければ定着しにくい傾向があります。その一方で、具体的で実用的な学習内容は理解できることが多く、適切な支援を受ければ学習の成果を積み重ねることができます。
友人関係やコミュニケーションの難しさ
会話やコミュニケーションにおいては、単純なやり取りは問題なく行えるものの、複雑な話題になると理解や表現に困難を感じやすいです。
このため、誤解が生じたり、友人関係が長続きしにくいことがあります。孤立感や自尊心の低下につながることもあるため、周囲の理解と支援が重要です。
就労や社会生活への影響
就労に関しては、複雑な判断や高度なスキルを必要としない業務であれば十分に対応可能です。
ただし、新しい環境に適応するのに時間がかかったり、仕事の手順を覚えるのに支援が必要なこともあります。社会生活では金銭管理や計画的な行動に苦手さがあるため、支援者や家族のフォローが求められるケースも少なくありません。
就労移行支援を利用するケース
社会参加を目指す軽度知的障害の方には、就労移行支援事業所の活用が有効です。
ここでは職業訓練や実習を通じて働くスキルを身につけ、一般就労や福祉的就労につなげることができます。専門スタッフのサポートを受けながら、自分の特性に合った働き方を見つけられる点が大きなメリットです。
軽度知的障害の問題点は?

軽度知的障害は日常生活を送るうえで大きな制約が少ないため、「問題はないのでは?」と思われることもあります。
しかし、軽度であっても知的障害である以上、本人や家族が抱える課題は少なくありません。ここでは代表的な問題点について解説します。
幼少期の発見が難しい理由
軽度知的障害は、乳幼児期には言葉の遅れや発達の差があまり目立たないことも多く、発見が遅れがちです。
多くの場合、小学校に入学してから学習や集団生活での困難を通じて気づかれるケースが一般的です。早期に診断や支援につなげることが難しいため、本人が苦労を抱えたまま成長してしまうことがあります。
意思疎通の困難さ
軽度知的障害の方は、日常的で単純な会話は問題なく行えますが、複雑な指示や抽象的な表現を理解するのが難しい場合があります。
そのため、誤解やコミュニケーションのすれ違いが起きやすく、友人や同僚との人間関係に影響することもあります。意思疎通の困難さは孤立感やストレスの原因となり、二次的な心の問題につながることもあります。
自尊心の低さと他者への依存性
学習や人間関係でつまずく経験を繰り返すことで、自尊心が低下しやすい傾向があります。また、自分に自信を持てないために、他者に依存しがちになることもあります。
場合によっては、不適切な人間関係に巻き込まれたり、トラブルや犯罪に巻き込まれるリスクも指摘されています。本人の安全を守るためにも、信頼できる支援者の存在が重要です。
周囲から理解されにくい現実
軽度知的障害は外見から分かりにくいため、「努力不足」や「やる気の問題」と誤解されやすい特徴があります。このような理解不足は、本人が社会の中で孤立したり、不当な扱いを受ける原因となります。
周囲が障害特性を正しく理解し配慮やサポートを行うことが、本人の生活の安定につながります。
軽度知的障害の診断方法は?

軽度知的障害は見た目や日常の様子だけでは判断しづらく、専門医による総合的な評価が必要です。
診断では医学的な検査に加え、日常生活での適応能力や行動の特徴を多角的に確認します。ここでは代表的な診断方法を紹介します。
原因疾患の有無を調べる
まずは、知的障害の背景に遺伝的要因や病気が存在するかを確認します。染色体異常、先天代謝異常、てんかん、先天性風疹症候群などが原因となるケースがあります。
こうした疾患が見つかった場合は、治療により症状の進行や合併症を抑えられる可能性があります。
日常生活の適応機能を評価する
知的障害の診断では、学力やIQだけでなく、日常生活で必要な力を評価します。
これは「概念的領域」「社会的領域」「実用的領域」の3つに分けられ、記憶力や言語能力、対人スキル、セルフケア能力などが確認されます。生活全体を支える力をどの程度持っているかを把握することが、診断の大切なポイントです。
日本版Vineland-II適応行動尺度
この検査は、同年代の一般的な行動と比較しながら、対象者がどの程度日常生活のスキルを持っているかを測定するものです。コミュニケーション能力、日常生活スキル、社会性などを客観的に評価できるため、支援方針を考える上で役立ちます。
WISC-IVやWAISなどの知能検査
知能指数(IQ)を測定するために行われる代表的な検査がWISC-IV(子ども向け)やWAIS(成人向け)です。
これらの検査では記憶力や推論力、処理速度などを細かく分析し、得意な部分と苦手な部分を把握することが可能です。結果をもとに、学習支援や生活支援の方法を具体的に検討していきます。
軽度知的障害の原因とリスク要因
軽度知的障害の発症にはさまざまな要因が関わっており、ひとつの原因だけで説明できるものではありません。遺伝的な背景、妊娠・出産時の影響、育ちや環境などが複合的に作用することが多いです。
原因やリスク要因を正しく理解することは、予防や早期支援につなげるうえで重要です。
遺伝的要因
知的障害の一部は遺伝によって生じることがあります。ダウン症や脆弱X症候群などの染色体異常、または代謝異常症などが代表例です。
家族に知的障害や発達障害がある場合、子どもに同様の傾向がみられる可能性があります。ただし、遺伝要因があったとしても、環境や支援によって発達の状況は大きく変化することがわかっています。
周産期の影響(妊娠中や出産時の要因)
妊娠中の母体の健康状態や、出産時のトラブルが軽度知的障害の要因となることがあります。妊娠中の感染症、栄養不足、アルコールや薬物の摂取などは胎児の脳の発達に影響を与える可能性があります。
また、出産時の仮死や低出生体重児、早産などもリスク因子のひとつです。母子の健康管理を徹底することは、リスクを軽減するために非常に重要です。
環境要因と育ちの影響
生まれた後の環境や養育状況も、知的発達に大きく関わります。極端な養育放棄や虐待、貧困による栄養不足などは、発達の遅れを引き起こす可能性があります。
また、家庭や教育環境で十分な刺激や学習の機会が与えられない場合、発達に影響が出ることもあります。適切な支援や教育を受けることで改善が期待できるケースも多いため、早期の介入が大切です。
軽度知的障害を治療・改善するには?

軽度知的障害は病気のように完治を目指せるものではありません。しかし、早期から適切な支援や療育を受けることで、生活の質や社会参加の可能性を大きく高めることができます。
ここでは、治療や改善に向けた代表的なアプローチを解説します。
障害そのものの改善は難しい
軽度知的障害は根本的に「治る」ものではありません。
ただし、適切な教育や支援を受けることでできることが広がり、自立した生活を送れる可能性が高まります。本人の特性を理解した支援方針を立てることが大切です。
療育や特別支援教育を受ける
幼少期からの療育は、発達を促し、社会生活に必要なスキルを育むために非常に有効です。
言語やコミュニケーションの訓練、運動や生活動作の指導などが行われます。また、学校では特別支援学級や通級指導教室を利用することで、本人に合った教育を受けることができます。早期の療育や特別支援教育は、自立に向けた大きな一歩となります。
家族や周囲からの支援が重要
軽度知的障害のある方にとって、家族や周囲の理解と支援は欠かせません。
否定的な言葉を避けできることを認めてサポートし、本人の自己決定を尊重する姿勢が自尊心の維持につながります。
また、家庭だけでなく学校や地域社会が協力し合うことで、安心できる環境が整い、本人の成長を促すことができます。
就労支援や福祉サービスの活用
大人になってからは、就労移行支援事業所や障害者雇用枠などを活用して働く道を広げることができます。さらに、福祉サービスを利用することで、生活全般におけるサポートを受けながら自立を目指せます。
行政の相談窓口や支援機関を通じて、利用できる制度を確認しておくと安心です。
軽度知的障害の方が利用できるサービス

軽度知的障害のある方は、学習・就労・生活面でサポートが必要となる場面があり、それぞれの状況に応じて利用できる支援制度が整えられています。
行政の福祉サービスや専門機関を上手に活用することで、地域で安心して暮らすための環境を整えることができます。ここでは、軽度知的障害のある方が利用できる代表的なサービスについて解説します。
療育手帳の取得方法とメリット
療育手帳は、知的障害の程度に応じて交付される手帳で、軽度知的障害の方も対象となります。
手帳を取得するには、自治体の障害福祉課で申請し、医師の診断や心理検査などを踏まえた判定を受ける必要があります。取得後は、税金の控除や交通機関の割引、福祉サービスの利用しやすさなど、生活面でのメリットが多くあります。
手帳を持つことによって必要な支援につながりやすくなるため、本人や家族の負担軽減にも役立ちます。
障害者雇用と福祉的就労の違い
働く場を選ぶ際、軽度知的障害の方には「障害者雇用」と「福祉的就労」という2つの選択肢があります。
障害者雇用は企業の雇用契約のもと働く制度で、給与や労働条件が一般的な雇用と同様に保障されます。一方、福祉的就労(就労継続支援B型など)は、体調や能力に合わせて無理なく働ける環境が整っている点が特徴です。自分に合った働き方を選べることが、長く働き続けるための大切なポイントです。
就労移行支援を利用すれば、職場定着のサポートを受けながら就職を目指すこともできます。
グループホームや生活介護など
生活面で支援が必要な軽度知的障害の方には、グループホーム(共同生活援助)や生活介護などの福祉サービスがあります。
グループホームでは、スタッフの見守りのもとで共同生活を送り、家事や金銭管理などの自立に向けたサポートを受けられます。生活介護では、日中活動の場として、創作活動や軽作業、健康維持のための運動などが行われます。
家庭だけでは支えきれない部分を補い、地域の中で安定した生活を続けるための支援が整っています。これらのサービスは自治体の相談窓口を通じて申請・利用の流れを確認できます。
軽度知的障害に関する相談窓口

軽度知的障害のある方やそのご家族は、適切な相談窓口を活用することで支援や制度を受けやすくなります。
相談先は年齢や状況によって異なり、児童期・成人期それぞれに対応した窓口が存在します。ここでは代表的な相談機関を紹介します。
自治体の福祉課や発達相談窓口
市区町村の福祉課や保健センターには、障害福祉に関する相談窓口があります。
子どもの場合は児童相談所や保健所での相談が可能で、発達の遅れや学習の不安について専門スタッフにアドバイスを受けられます。成人の場合は、障害福祉課で生活支援や制度利用について案内してもらえます。
発達障害者支援センター
全国に設置されている発達障害者支援センターでは、発達障害や軽度知的障害のある方やその家族を対象に幅広い支援を行っています。
生活や就労に関する相談だけでなく、教育機関や医療機関と連携して包括的な支援を提供する点が特徴です。専門的な視点から助言を受けられるため、安心して相談できる場所といえます。
医療機関・クリニックでの相談
小児科や精神科、心療内科などの医療機関でも相談が可能です。
発達の遅れが気になる場合には早めに医師に相談し、必要であれば知能検査や心理検査を受ける流れとなります。医療機関で診断が確定すれば、療育や福祉制度につなげることができ、支援の幅が広がります。
精神科訪問看護を利用するという選択肢も

軽度知的障害のある方は、就労や生活の中で困難を抱えることがあります。
そのようなときに役立つ支援のひとつが精神科訪問看護です。医療専門職が自宅を訪問し、本人や家族を支えるサービスで、安心して生活を続けるための有効な選択肢となります。
精神科訪問看護とは?
| サービス名 | 精神科訪問看護 |
|---|---|
| ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得 対人関係の維持など |
| 訪問日数 | 原則 週3日以内 |
精神科訪問看護は、精神疾患や発達障害、知的障害のある方を対象に、看護師や作業療法士が自宅へ訪問し支援を行う制度です。
医師の指示のもと、病状の観察や服薬管理、日常生活のアドバイスなどを提供します。外出が難しい方や、通院だけでは十分な支援を受けにくい方にとって大きな助けとなります。
精神科訪問看護のサポート内容
サポート内容は多岐にわたり、症状コントロールや健康管理、服薬支援、生活スキルの習得、再発予防などがあります。
さらに、家族への助言や社会資源の活用サポートも行うため、本人だけでなく周囲の安心にもつながります。医療と生活の両面を支える点が大きな特徴です。
軽度知的障害の方が受けられる支援
軽度知的障害のある方は、日常生活の管理や就労の継続に不安を抱えることが少なくありません。
精神科訪問看護では、服薬の確認や生活リズムの調整、対人関係に関する相談など、実際の生活に直結した支援を受けられます。これにより、自立を促しながら地域社会の中で安定した生活を送ることが可能になります。
精神科訪問看護ならシンプレ看護ステーションへ!

軽度知的障害の方が安心して生活を送るためには、地域でのサポート体制が欠かせません。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患や知的障害に特化した専門的な訪問看護を行っており、一人ひとりの状況に合わせたケアを提供しています。
シンプレ訪問看護ステーションの看護内容
当ステーションでは、生活支援・社会復帰のサポート・服薬支援・病状の観察や再発防止など、多岐にわたるサービスを提供しています。
対象となる疾患には、うつ病・統合失調症・発達障害・知的障害・認知症などが含まれます。利用者様が住み慣れた環境で安心して暮らせるよう、きめ細かな看護を行うことを大切にしています。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリアは、東京23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、さらに埼玉県の一部地域まで幅広く対応しています。エリア外でも訪問可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

軽度知的障害は外見からは気づかれにくい一方で、学習や人間関係、就労において特有の困難を伴うことがあります。正しい理解と早期の支援が、本人の自立や生活の安定につながります。ここまでの内容を整理し、まとめておきましょう。
軽度知的障害の特徴を正しく理解することが大切
軽度知的障害はIQ50〜69程度とされ、日常生活はある程度自立できますが、学習や抽象的な思考には困難があります。
特性を理解することで、本人の強みを活かしながら支援につなげることが可能です。
早期発見と適切な支援で生活の質は向上できる
幼少期には気づかれにくいため、小学校以降に判明することが多いですが、早めに支援につなげることで学習や生活の困難を軽減できます。療育や特別支援教育、福祉制度の利用は生活の質を大きく向上させる手段となります。
家族・学校・医療・福祉が連携してサポートする
本人を支えるためには、家族だけでなく学校や医療機関、福祉サービスが連携することが大切です。
多方面からの支援が整うことで、本人の不安が和らぎ、社会生活への適応が進みます。
精神科訪問看護や相談窓口の活用も有効
生活や就労に不安を抱える場合は、自治体の福祉課や発達障害者支援センター、精神科訪問看護などのサポートを活用することをおすすめします。
外部の専門的な支援を取り入れることで、安心して地域で暮らし続けることができます。
ご相談の問い合わせはこちら▼

高座渋谷つばさクリニック
医師:武井智昭
外来としてはうつ病(うつ状態)が年間300名程度はおりこちらが得意分野です。この他に、思春期特有の対応(起立性調節障害や拒食症など)も行っています。心療内科としては10年、日本精神神経学会会員に所属
本記事へのコメント
軽度知的障害は、外見からは分かりにくいため、周囲に理解されず苦労されている方も多いと思います。大切なのは、これは「病気」ではなく「発達の特性」であり、適切な支援があれば十分に社会生活を送れるということです。
診断を受けることは、決してマイナスではありません。むしろ、療育手帳の取得や福祉サービスの利用、就労支援など、さまざまなサポートを受けられる扉が開き、様々な支援が受けられます。
私たちは、専門医療機関や福祉・教育機関と連携しながら、皆様の健康と生活全体を見守ります。「できないこと」ではなく「できること」に目を向け、その方らしい生き方を一緒に探していきましょう。
ご家族の負担も大きいと思います。みんなで支え合いながら、安心できる暮らしを築いていきましょう。
監修日:2025年11月18日
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



