チック障害の症状を徹底解説|種類・原因・治療・接し方をわかりやすく紹介
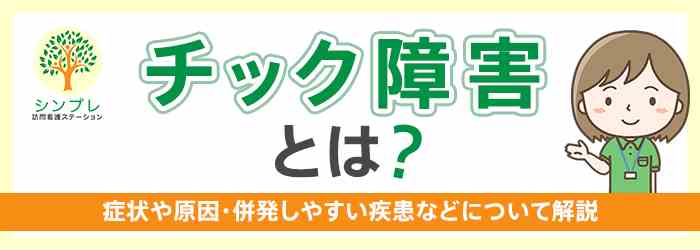
チック障害の症状は、突然のまばたきや首・肩の動き、発声など、本人の意思に関係なく現れる特徴的な動作が見られます。
多くの場合、症状は一時的なものですが、繰り返し起こるケースも少なくありません。
この記事では、チック障害の症状やその種類、原因、治療方法などをわかりやすく解説します。
症状に悩んでいる方やご家族の方は、ぜひ参考にしてください。
チック障害の症状とは?代表的な種類を解説
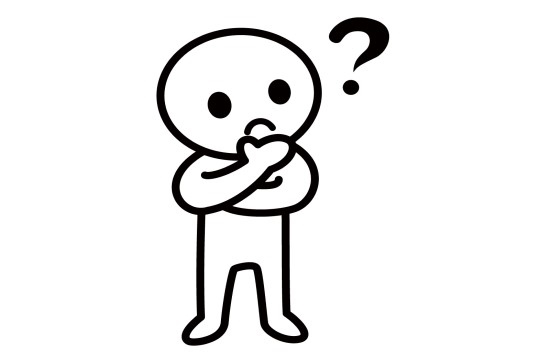
チック障害には、運動チックと音声チックの2種類があり、それぞれ「単純」と「複雑」に分けられます。
どのタイプも共通して、不随意に動いたり声を出してしまうといった特徴があり、本人の努力では完全に止めることが難しいのが特徴です。
単純運動チック(まばたき・肩すくめなど)
- まばたき
- しかめ顔
- 白目をむく
- 首や肩をすくめる
単純運動チックは、顔や首、肩など上半身に多く見られる症状で、チック障害の初期に現れることが多いです。
例えば「まばたきが頻繁に出る」「顔をしかめる」「首を振る」など、一瞬で終わる動作が特徴です。
これらの症状は、緊張や疲労、ストレスによって一時的に悪化することもあります。
単純音声チック(咳払い・鼻鳴らしなど)
- せきばらい
- 鼻をすする
- うめき声・短い発声
単純音声チックは、喉や鼻などから音を発してしまう症状で、「アッアッ」などの声や鼻ならしが代表的です。
静かな環境では目立ちやすく、本人が気にしてストレスを感じることもありますが、
無理に止めようとすると逆に強く出る傾向があります。
複雑性運動チック(ジャンプ・身振り動作など)
複雑性運動チックは、複数の筋肉が同時に動くことで生じる症状です。
例えば、飛び跳ねたり、自分の体を叩いたり、他人や物に触れるなどの動作がみられます。
動作が大きく、誤解を受けることもあるため、周囲の理解がとても大切です。
複雑性音声チック(単語やフレーズを発する)
- 言葉の繰り返し(反響言語)
- 不適切な言葉を発する(汚言)
複雑性音声チックでは、無意識に単語やフレーズを繰り返したり、不適切な言葉を発してしまうことがあります。
特に「汚言(おげん)」は本人の意思とは無関係に出てしまうため、強い悩みを抱える方も少なくありません。
運動と音声が両方見られる場合もある
運動チックと音声チックの両方が1年以上続く場合、「トゥレット症候群」と診断されることがあります。
症状の頻度や種類は人によって異なりますが、6歳前後に発症し、思春期をピークに軽快するケースもあります。
トゥレット症候群は男性に多く見られ、約1万人に1〜5人の割合で発症するといわれています。
チック症の原因について
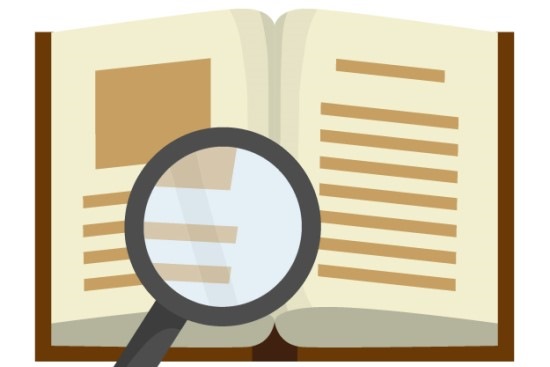
チック症の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れや遺伝的要因が関係していると考えられています。
特に、ドーパミンと呼ばれる神経伝達物質の過剰な働きが、運動や発声を抑える機能に影響を与え、チック障害の症状を引き起こす一因になるとされています。
脳内神経伝達物質の関与
脳の神経細胞同士は、ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質によって情報をやり取りしています。
ドーパミンは「やる気」や「快感」を感じるために必要な物質ですが、過剰に分泌されると脳の抑制機能が低下し、無意識の動きや発声といったチック障害の症状が出やすくなると考えられています。
そのため、ドーパミンの働きを調整する薬が治療に使われることもあります。
これは、チック症が単なる「癖」や「性格の問題」ではなく、脳の神経活動に関わる医学的な要因によって引き起こされる疾患であることを示しています。
遺伝的要因や環境要因
チック症は、家族の中に同様の症状を持つ人がいるケースが報告されており、遺伝的な傾向が関係していると考えられています。
ただし、遺伝だけで発症するわけではなく、ストレスや環境の変化などが加わることで症状が現れたり悪化することがあります。
たとえば、学校や職場での緊張、家庭内での不安、疲労の蓄積などがストレスとなり、チック症の症状を一時的に強めることがあります。
反対に、安心できる環境や理解ある周囲のサポートがあると、症状が軽くなることもあります。
このように、チック症は遺伝的な体質と環境要因の両方が影響し合って発症すると考えられています。
そのため、医師や専門スタッフと連携し、ストレスを減らす生活環境の整備を行うことが大切です。
チック症の診断方法
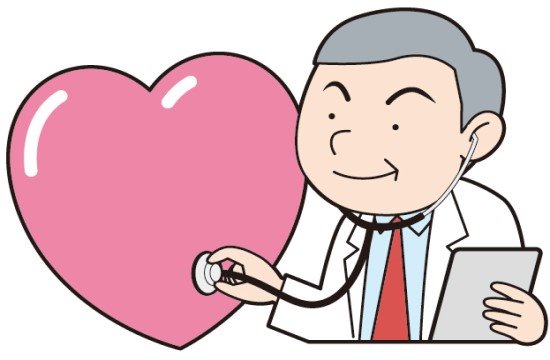
チック症の診断は、問診や行動観察を中心に行われる臨床的な評価によって進められます。
特別な検査で「陽性」や「陰性」が出るわけではないため、医師が本人や家族からの聞き取りを通じて症状の出方や頻度、期間などを確認します。
チック障害の症状は一時的に軽くなったり消えたりすることもあるため、発症からの経過を丁寧に観察することが大切です。
問診や行動観察による診断
診察では、まずいつからチックのような動きや声が出始めたのか、どのくらいの頻度で出るのかなどを詳しく聞かれます。
また、ストレスを感じる場面で症状が悪化するか、休息時や睡眠中に軽減するかといった点も確認されます。
医師は本人の行動を直接観察し、チック障害の症状が他の病気によるものではないかを判断します。
ときには動画の記録を参考に診断を進めることもあります。
チック症は、「本人の意思で止められない」「繰り返し出る」という特徴をもとに見極められます。
発作的な動作や声を出す症状が見られても、それが癖やストレス反応なのか、チック症なのかを正確に判断するためには専門医の診察が欠かせません。
DSM-5など診断基準を用いた評価
診断には、アメリカ精神医学会が定める「DSM-5」という国際的な診断基準が用いられます。
この基準では、18歳以前に発症していること、1年以上にわたって運動チックや音声チックが続いていること、そして他の疾患や薬の副作用では説明できないこと、などが判断のポイントになります。
チック症は一過性の場合もありますが、1年以上続く場合は「持続性運動チック症」または「持続性音声チック症」と診断されます。
さらに、運動チックと音声チックの両方が見られる場合は「トゥレット症候群」とされます。
チック障害の症状は、本人や家族が「癖」と思い込んで見過ごしてしまうことも少なくありません。
しかし、早期に専門医に相談することで、適切な支援や治療につながる可能性が高まります。
気になる動作や発声がある場合は、早めに受診を検討しましょう。
チック症に併発しやすい疾患

チック障害の症状は、単独で現れることもありますが、他の精神疾患や発達障害を併発するケースも少なくありません。
特に、ADHD(注意欠如・多動症)や強迫性障害(OCD)、不安障害などとの合併が多いことが知られています。
併発することで症状が複雑化しやすく、本人の生活や学習、対人関係にも影響を及ぼすことがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)
ADHDは、注意力の持続が難しかったり、衝動的に行動してしまったりする発達障害です。
チック障害とADHDを併発している人は少なくなく、集中力の低下や落ち着きのなさが加わることで、学校や職場での困難が生じやすくなります。
両者が重なることで、「動きが多く落ち着かない」「不注意によるミスが増える」などのチック障害の症状がより目立つこともあります。
また、ADHDの特徴である「衝動性」や「不安の感じやすさ」がチック症状を誘発する場合もあります。
本人だけでなく、周囲の理解や支援が必要です。
強迫性障害(OCD)
チック症では、「やりたいけどやってはいけない」といった葛藤を伴う“前駆衝動”と呼ばれる感覚がみられることがあります。
この特徴は、強迫性障害に見られる強迫行為や強迫観念と似ています。
そのため、チック症と強迫性障害が併発するケースも多く、繰り返し行動を取ってしまうことが本人のストレスとなります。
強迫性障害が加わると、チックによる無意識の動きに加えて、意図的に「何度も確認する」「手を洗う」などの行動が増えることがあります。
こうした症状が重なると、日常生活に大きな負担を感じるようになるため、専門的な治療やカウンセリングが重要です。
不安障害や学習障害
チック症の背景には、強い緊張や不安が関係していることもあり、不安障害を併発するケースも見られます。
不安が高まるとチック症状が悪化し、さらに「周囲に見られるのが怖い」という気持ちから外出や会話を避けてしまうこともあります。
また、学習障害(LD)を併発している場合、学習環境でのストレスがチック障害の症状を強めることもあります。
本人が安心して過ごせるよう、教育機関や医療機関が連携してサポートすることが大切です。
このように、チック症は単独でなく他の疾患と関係することが多いのが特徴です。
併発している症状を見極めながら、包括的な支援を受けることで生活の質を高めることができます。
チック症の治療方法

チック症の治療方法は、症状の重さや生活への影響度によって異なります。
多くの場合、本人や家族が病気を理解し、ストレスの少ない環境を整えることが治療の第一歩となります。
症状が軽度であれば経過観察が選択されることもありますが、学校や仕事など日常生活に支障がある場合は、心理的支援や薬物療法が検討されます。
心理教育・環境調整による支援
心理教育とは、本人や家族がチック症に関する正しい知識を持ち、症状と上手に付き合うためのサポートを受けることです。
チック障害の症状はストレスや緊張で悪化しやすいため、周囲の理解が何より大切です。
家族や学校の先生が「無理に止めさせない」「叱らない」といった関わり方をすることで、安心して過ごせる環境が整い、症状が軽くなることがあります。
また、生活リズムの乱れや睡眠不足もチック症の悪化につながるため、規則正しい生活習慣を維持することが重要です。
本人がリラックスして過ごせる環境をつくることが、治療の基本になります。
薬物療法で症状をコントロール
チック症が重度で、心理的支援だけでは改善が難しい場合には薬物療法が行われます。
薬物療法では、ドーパミンの働きを調整する抗精神病薬や、興奮を抑える薬などが使用されることがあります。
これにより、動作や発声といったチック障害の症状を軽減させる効果が期待できます。
また、強迫性障害やADHDなどの併発症がある場合は、それぞれの症状に合わせた薬の処方が検討されます。
薬はあくまで症状をコントロールする手段のひとつであり、心理的なサポートや生活環境の改善と併用することが効果的です。
薬の種類や量は人によって異なり、副作用の有無や日常生活への影響を見ながら医師が慎重に調整します。
医療機関で定期的な診察を受けながら、症状の変化に応じて治療方針を柔軟に見直していくことが大切です。
チック症の治療では、「治す」ことだけを目標にするのではなく、「症状とうまく付き合う」ことも重要です。
周囲の理解とサポートを得ながら、本人のペースに合わせて前向きに取り組んでいくことが、改善への近道といえるでしょう。
チック症の方との接し方

チック症の方と接する際には、症状を無理に抑えさせず、自然に受け入れる姿勢がとても大切です。
チック障害の症状は本人の意思でコントロールできるものではなく、緊張やストレスによって強く出てしまうこともあります。
そのため、周囲の人が「やめなさい」「落ち着いて」と指摘すると、かえって症状が悪化してしまうことがあります。
症状を無理に抑えさせない
チック症は、本人が「やってはいけない」と思いながらも止められないという特徴があります。
特に子どもの場合、周囲から叱られたり注意を受けたりすることで、ストレスが高まり症状が強くなることがあります。
チック障害の症状を理解し、無理に抑えさせようとしないことが何より重要です。
また、症状が出ているときに「落ち着いて」「我慢して」と言うのではなく、「大丈夫だよ」「少し休もうか」と安心させる言葉をかけるようにしましょう。
本人が安心できることで、症状が落ち着くこともあります。
安心できる環境づくりを意識する
チック症は、ストレスや環境の変化に影響されやすい疾患です。
そのため、安心して過ごせる環境づくりが大切になります。
家庭や学校、職場で過度なプレッシャーを与えず、リラックスできる時間を確保することを意識しましょう。
特に家庭では、規則正しい生活リズムを整え、十分な睡眠を取ることも症状の軽減につながります。
また、本人が好きな活動や趣味に取り組める時間を持つことで、気分転換や自信の回復にもつながります。
周囲の人がチック障害について理解を深めることで、本人も安心して生活を送ることができます。
症状を否定せず、受け止めながら支える姿勢を持つことが、回復や社会適応への第一歩となるでしょう。
もし家庭や学校だけで対応が難しい場合は、医療機関や訪問看護などの専門サービスを活用するのも有効です。
専門職によるサポートを受けることで、本人も家族も安心して過ごせるようになります。
精神科訪問看護という選択肢もある

チック障害やうつ病、発達障害など、外出や通院が難しい方にとって、自宅で医療的な支援を受けられる「精神科訪問看護」は有効な選択肢です。
精神疾患を抱える方が、住み慣れた環境で安心して生活を続けられるように、看護師や作業療法士などの専門職が自宅に訪問して支援を行います。
精神科訪問看護とは?
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護の専門職
・リハビリテーションの専門職
訪問時間
・医療保険
(30分から90分程度)
精神科訪問看護は、看護師やリハビリ専門職が利用者のご自宅を訪問し、医療的ケアや生活支援を提供するサービスです。
チック障害の症状によって外出が不安な方や、他の精神疾患で生活リズムが乱れがちな方にとって、在宅でサポートを受けられることは大きな安心につながります。
訪問看護で行う具体的なサポート内容
訪問看護では、服薬支援や症状の観察、生活リズムの調整、社会復帰への支援など、利用者一人ひとりに合わせたケアを行います。
また、ご家族へのアドバイスや相談対応も含まれるため、本人だけでなく家族も安心して支援を受けることができます。
・自立した生活を営めるための支援
・生活リズムの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・生活状況を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
精神科訪問看護を利用するメリット
- 自宅に居ながら専門的なケアが受けられる
- 自宅での様子を主治医に連携できる
- 対人関係や日常生活の支援を受けられる
精神科訪問看護の最大のメリットは、自宅にいながら医療的ケアや心理的サポートを受けられることです。
外出が困難な方や、対人関係のストレスを感じやすい方も、安心して支援を受けられます。
また、訪問スタッフが定期的に様子を確認することで、症状の変化を早期に察知し、医師と連携して適切な対応を行うことができます。
これにより、再発予防や体調の安定にもつながります。
訪問看護の料金と自己負担額
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担 | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担 | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担 | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
自立支援医療(精神通院医療)の活用
精神科訪問看護を利用する際は、「自立支援医療制度(精神通院医療)」を活用することで自己負担額を軽減できます。
この制度を利用すると、医療費の自己負担が原則1割となり、所得に応じて月の上限額が設定されます。
上限を超えた分は公費負担となるため、経済的な負担を抑えて継続的な支援を受けることが可能です。
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
精神疾患のケアならシンプレ訪問看護ステーションへ

シンプレ訪問看護ステーションの特徴
チック障害をはじめとした精神疾患は、早期に専門的な支援を受けることで、症状の悪化を防ぎ、安定した生活を取り戻すことが可能です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、看護師・准看護師・作業療法士がチームとなり、精神疾患に特化したサポート体制を整え、利用者一人ひとりが自分らしい生活を送れるよう、寄り添ったケアを提供しています。
チック障害の症状や不安を抱える方に対しても、服薬支援やストレスケア、生活リズムの安定化など、安心して生活を続けられるようサポートしています。
訪問時間は1回あたり30〜90分、週1〜3回の訪問を基本としていますが、症状や生活状況に応じて週4回以上の訪問も可能です。
祝日や土曜も訪問を行っているため、急な体調の変化にも柔軟に対応できます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
シンプレは、東京都23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市および埼玉県一部エリアで訪問看護を行っています。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|チック障害の症状を理解し正しい支援へつなげよう

チック障害は、無意識の動きや発声といった症状が繰り返し現れる神経発達症の一つです。
まばたきや首振りといった軽い動作から、声を出す症状まで幅広く、症状の程度も人によって異なります。
そのため、チック障害の症状を「癖」と誤解せず、医学的な支援が必要な疾患であることを理解することが重要です。
チック症は成長とともに軽快することもありますが、強いストレスや環境の変化によって再び症状が出ることもあります。
大切なのは、焦らず、見守りながら適切な支援を受けることです。
家族や周囲の理解が得られるだけでも、本人の安心感が高まり、症状が落ち着く場合があります。
また、チック障害に限らず、ADHDや強迫性障害、不安障害などを併発するケースもあります。
症状が長く続く、または日常生活に支障を感じる場合には、早めに専門医やカウンセラーへ相談しましょう。
もし外出や通院が難しい場合には、精神科訪問看護を利用するという選択肢もあります。
看護師や作業療法士が自宅で支援を行い、服薬のサポートや生活リズムの調整、再発防止のケアなどを提供してくれます。
安心できる環境の中で治療を継続することができるでしょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、チック障害を含む精神疾患に特化した看護サービスを提供しています。
専門職によるサポートと温かい関わりで、利用者が自分らしい生活を取り戻せるよう支援しています。
チック障害の症状に悩んでいる方やご家族の方は、ひとりで抱え込まずに、ぜひ一度シンプレ訪問看護ステーションへご相談ください。
あなたの気持ちに寄り添いながら、回復への一歩を一緒に歩んでいきます。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2026年2月 (5)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)



